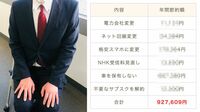子どもの習い事で多発する「応援席ハラスメント」の実態とは? スイミングではライバルの母親が「溺れろ!」と暴言
試合で選手がミスをすると、わが子であっても他人の子であっても「何をやっているんだ!」と保護者が罵声を浴びせる。
わが子が他人の親に怒鳴られた保護者も、「チームが強くなるためには仕方ない」と受け入れてしまう傾向があるという。
親がわが子に「同一化」してしまう
「『応援席ハラスメント』に及ぶ保護者は、基本的にわが子と同一化してしまう傾向が認められます。個人競技だと、わが子ではなく自分自身が挑戦している気になってしまう。
団体競技ならわが子のチームではなく、自分のチームになる。わが子やわが子のチームが敗れてしまうと、保護者は自分の自己評価も下がったように感じてしまうのです」(藤後教授)
他人の子どもに露骨な敵意を示す応援席ハラスメントも珍しくない。個人競技の場合は、子ども同士の競争が原因となるが、団体競技では、さらに「コーチの目指すチーム作り」も火種のひとつになるという「水泳ならタイムの速い子に、遅い子の保護者が暴言を吐くわけです。
野球やサッカーも同じですが、コーチ が目指すチーム方針、たとえば攻撃重視か守備重視かで、起用する子どもの顔ぶれが変わることがあります。その場合、一定の実績を上げていても控えに回る子が出てくるわけです。
わが子が先発出場できないことに強い不満を持ち、レギュラーの子どもに向かって応援席ハラスメントに及ぶ保護者もいます」(藤後教授)
セクハラやパワハラなどのハラスメントは昭和の方が蔓延していたが、応援席ハラスメントは2000年以前には今ほど多くは見られなかった現象だという。
「昭和の頃は子どもにスポーツを習わせる場合でも、保護者が練習や試合に顔を出すことは多くありませんでした。現在の保護者のほうが子育てにコミットメントする傾向が強くなっています。
この傾向は、教育虐待の問題とも通底しています。中学受験は保護者がわが子の勉強をサポートすることが求められます。
受験をするわが子に親が同一化して、『何で偏差値が上がらないの!?』と子どもを詰問してしまうのは、まさに応援席ハラスメントと同じ精神状態に陥っているのです」(藤後教授)
本来であれば、習い事で他の子と切磋琢磨(せっさたくま)できるのは貴重な体験のはずだ。親だからこそ“他者への寛容性”を持って、頑張る子どもたち全てに声援を送るべきだろう。
(井荻稔)
記事をマイページに保存
できます。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら
印刷ページの表示はログインが必要です。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら