「ネズミの死骸入り味噌汁か。会社潰れるんじゃ?」→「軽微なダメージでした」 すき家「ネズミ混入でも影響小」が示す”残酷な現実”
一方、「であれば、松屋か吉野家に客が流れるのでは?」と思う人もいるだろう。実際、今回の「ネズミソ汁」騒動を受けて同業他社に流れた客もいるに違いない。
ただ、それでも「すき家」が強いのは、その立地に秘密がある。というのも、同業他社である吉野家・松屋と比べた場合、すき家は地方・郊外に店舗が多いのだ。
実際、店舗数の分布を見てみると、松屋は全店舗のうち、約半数近くが関東圏に固まっている。吉野家は松屋よりは全国に分布しているものの、例えば四国の全店舗数は28店舗であり、すき家の60店舗に対して手薄になっている。他の地方でも往々にしてすき家の方が圧倒的な店舗数を誇っている。
これは、すき家が吉野家・松屋への逆張り戦略として郊外のファミリー層をターゲットにして店舗展開を行っていった歴史があるからだが、全国に張り巡らされた店舗網によって「すき家しかない」地域が生まれている。
そうなると、真の意味で日本のインフラとして機能しているのが「すき家」ということになるかもしれない。「インフラ」に好きも嫌いもない。単に必要だから行く。そんな状態がすき家にはある。つまり、積極的というよりも消去法的にすき家を利用しているのだ。
民間企業が結果的にインフラになる現代
「インフラ」という話でいえば、牛丼各社も「インフラ」としての牛丼屋を意識した施策を取っている。
例えば、吉野家は先日、牛丼大盛りを696円から740円へと値上げした。牛丼として700円を超えてくると「少々高いな……」と思う人がいてもおかしくない。
一方で牛丼並の価格については、据え置いて税込み498円のままにしている。プライシングスタジオ代表取締役CEO・高橋嘉尋氏はこの施策について興味深い指摘をしている。
高橋氏によれば、値上げをしても客足が離れない店は、その店で最も人を集めることができる「集客商品」の値段を維持する傾向がある。集客商品を値上げしてしまえば、その店を最も使うコアユーザーが離れてしまうからだ。吉野家はまさに「集客商品」の価格を維持している。
同社にとっての集客商品は「牛丼並」であり、その価格をワンコインにすることで、来店頻度の高いリピーターを繋ぎ止めているのだ(なぜ吉野家は「並盛498円」を値上げしなかったのか…深刻な客離れを起こした「スシローとガスト」との決定的違い・PRESIDENT Online/2025年5月7日)。
逆に言えば、吉野家が牛丼並に500円以上の価格をつけることができないのは、もはやそれがインフラになっていて、おいそれとは値上げできないからでもある。まさに「インフラ」としての牛丼屋の姿がそこにある。
話が少し横にそれてしまったが、いずれにしても「社会インフラ」としての牛丼屋、さらにその中でも地方・郊外にまでびっしり店舗があるすき家の「インフラ感」はかなり強いと思われる。
折しもコメの価格は上昇を続けており、農政の失策を批判する声が相次いでいる。それに加えて社会保障の負担などもどんどんと上昇しており、本来の「インフラ」には期待できないな……という社会的な機運も醸成されている。そんな中、少し倒錯的ではあるが一般企業の活動が「インフラ的」になっている現状があるわけだ。
すき家があれほどの事件で話題になったにもかかわらず、ここまでの業績を維持できる背景には、このような日本の姿があるのではないだろうか。

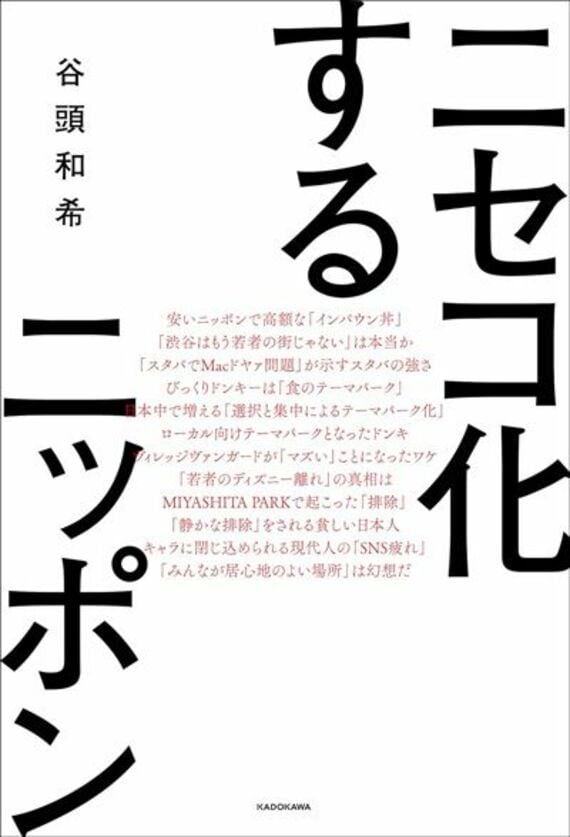
































無料会員登録はこちら
ログインはこちら