不安の共有が共同体を作る時代だ
「不安の共有」「不安からの連帯」は、今回のSNSの投稿から派生したようなデマや誤情報に飛び付きやせさすく、かつナショナリズム的な言説と容易に結び付きやすい。
また、いくら科学的な知見に基づくリスクコミュニケーションを徹底させても、特定のリスクを過大評価したり、あるいは注目が集まりやすいもっともらしい物語に引き付けられる事態が起こり得る。「すき家」の異物混入騒動がいとも簡単に陰謀論に転化してしまったように。
加えて、政治団体や宗教団体などが衰退した現代においては、健康に直接関係する出来事についての「不安の共有」「不安からの連帯」こそが集団的な熱狂を作り出している面もある。特に昨今は、誰とも社会的な絆を持ち得ないという連帯の貧困も絡んでおり、SNSを介した瞬間的なトレンドがその熱狂のお膳立てをし、一時の高揚感を与えてくれるのである。そのため、極端な方向へと暴走する懸念もある。
結局のところ、わたしたちが「毒物」的なものに敏感になるのは、リスク社会の宿命といえるが、年々高まる傾向にある健康への関心がそれを後押ししていることを忘れてはいけない。つまり、もはや頼りにできるリソースが自己の身体しか残されておらず、ちょっとしたアクシデントが致命傷になりかねないという酷薄な現実に促されているのだ。
「安全というユートピア」を目指しているとされるわたしたちの社会が何に突き動かされているのか。その内実に今一度目を向ける必要があるだろう。
記事をマイページに保存
できます。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら
印刷ページの表示はログインが必要です。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら

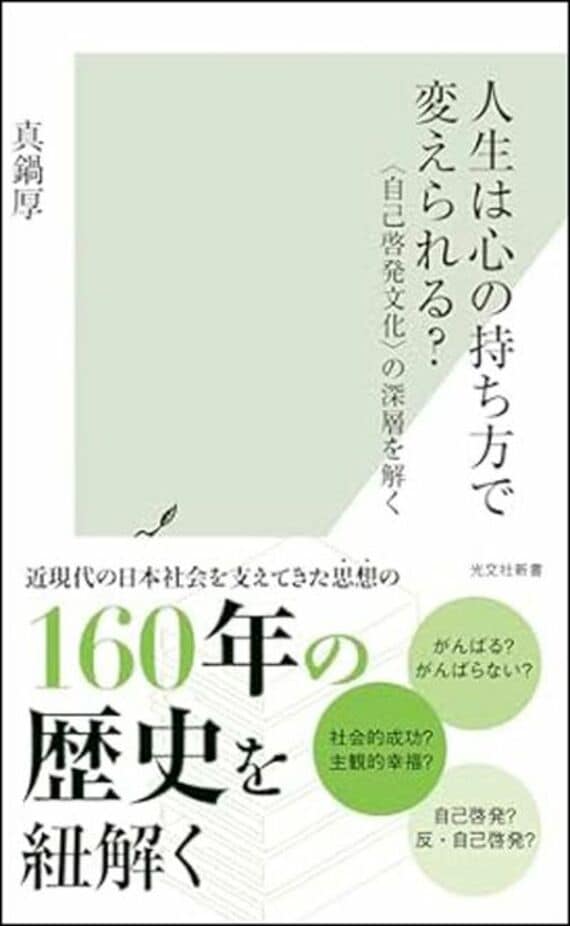
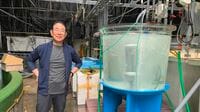





























無料会員登録はこちら
ログインはこちら