ちなみにゲノム編集とは、対象となる生物がもともと持っている特徴(特定の遺伝子)を改変する技術で、持っていない特徴(異なる種の遺伝子など)を追加する遺伝子組み換えとは異なる。
ゲノム編集の魚類では、筋肉の発達を抑える遺伝子をゲノム編集技術により働かないようにして可食部が増加した「肉厚マダイ」や、食欲を抑える遺伝子を働かないようにして少ない飼料で早く成長する「高成長ヒラメ」などが知られている。
なぜ、ゲノム編集はセンシティブになった?
遺伝子組み換え食品やゲノム編集動物食品に関するトピックがとりわけセンシティブなものになるのは、そのリスクが不確定であるからだ。特に新しいテクノロジーは、専門家ですら将来的にどのような悪影響が生じ得るのかが見通しづらいところがある(例えば、長期的に見てどのようなリスクがあるのか、どのような複合リスクがあるのかなど)。そのような視点に基づくリスク管理の方法の1つに、予防原則というものがある。
予防原則は、新技術などが環境や生態系に重大かつ不可逆的な影響を及ぼす恐れがある場合、科学的に因果関係が十分証明されない状況でも規制措置を可能とする考え方のことだ。具体的な被害が生じた後の回復などよりも、被害を未然に防止することを重視する。おそらくそれに似たリスクに対する見積もりが、食卓に上がるかもしれないゲノム編集食品などへの漠然とした不安につながっている。
このような不安を誘発するメカニズムは、社会学者のウルリヒ・ベックが1980年代に唱えたリスク社会論ですでに示されていたものだ。ベックは、現代社会の特性を環境破壊、原発事故、テロリズムなどといったグローバルなリスクと不確実性という側面から分析した。そして、「危険社会には、『不平等』社会の価値体系に代わって、『不安』社会の価値体系が現れる」と述べた(『危険社会 新しい近代への道』東廉・伊藤美登里訳、法政大学出版局)。
「安全というユートピアは消極的で防御的である。ここでは、『良い物』を獲得することは、もはや本質的な問題ではない。最悪の事態を避けることだけが関心事となる。階級社会の夢とは、すべての人々がケーキの分け前にあずかれることを欲し、すべての人々がその分け前にあずかるのが当然だというものである。これに対して、危険社会の目標は、すべての人々が毒物の被害をうけなくてもすむべきだ、というものである」と指摘。
「階級社会の原動力は、『渇望がある』という言葉に要約できるとしたら、危険社会を進展させる運動エネルギーは、『不安である』という言葉で表現できよう。つまり、危険社会では、階級社会にみられる欠乏の共有に代わって、不安の共有がみられる。この意味で、危険社会という社会形態の特徴は不安からの連帯が生じ、それが政治的な力となることにある」と主張した。
この「毒物の被害」という言葉における「毒物」には、単に特定の化学物質やウイルスだけでなく、遺伝子組み換えされたもの、ゲノム編集されたもの、その他新技術が用いられているリスクが不透明なものすべてが該当するだろう。
このベックの鋭い記述は、世界的な反コロナワクチン運動の台頭を説明するだけでなく、新技術が外国勢力という国外のエージェントによる災いの象徴として認識され得る背景を解き明かすものになっている。

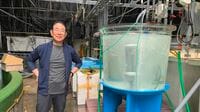





























無料会員登録はこちら
ログインはこちら