窪田:非認知能力が大事だとは思いつつも、受験戦争を勝ち抜くために、親御さんたちが学力重視になってしまう気持ちもわかります。とすると、子供たちの無限の可能性を伸ばすには、入試制度を変えるしかないのでしょうか?
中室:たしかに入試制度を変えることは、非常に有用な手ではあると思います。入試制度は人々の行動を強く規定しているからです。ただ、私はもっと幼児教育や小学校の低学年の教育を質の高いものにしていくことが必要だと思います。さまざまな研究が、幼少期の教育投資の収益率が高いことを示しているからです。
幼児期に教育を先取りすると、学力が伸びなくなる?
窪田:子供が小さければ小さいほど、教育の重要性は高まるのですね。
中室:はい。ただ、それは早期教育をすればよい、ということを意味しません。アメリカのテネシー州では、小学校入学後に有利になるようにとの考えから、読み書きや計算に力を入れた早期教育を行っていたのですが、こうした早期教育の効果はごくわずかの初期の間しか持続せず、すぐにそれをしなかった子供に追いつかれてしまったということが明らかになったのです。
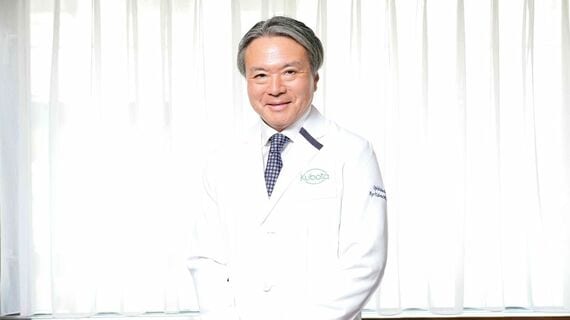
複数の研究が、アメリカの幼児教育は、特に2000年以降に読み書き・計算などの学力重視の指導に転換してから、幼児教育の効果がほとんど見られなくなったとか、あるいはマイナスの効果があったと指摘しています。例えば、2000年から2011年にかけて行われた幼児教育の効果は、1960年から1999年にかけて行われた幼児教育の2分の1程度しかなく、その効果が比較的早い段階で消滅することもわかっています。
窪田:小学校の教育を先取りしたことで、かえって悪い影響が出てしまったと。
中室:そうなんです。指導者の数が限られているのに、読み書きや計算を教えようと思うと、小学校のようにクラス単位の集団指導をせざるをえません。
しかし、そもそも幼児に、じっと座って、大人の話を大勢で聞くような集団指導は難しい。それが指導者側の焦りや厳しさを誘発し、子供の問題行動を悪化させたことが報告されています。
つまり、早期の先取り教育によって、一時的に学力にプラスの効果があっても、行動や情緒の面でマイナスの影響があり、ほとんど相殺されてしまっているというのです。































