スマホじゃなくて「あえて紙?」 東大生が《紙の日記》にこだわる深い理由 勉強ができる要因はここにあった!
だからこそ、書く内容自体はなんでもいいのです。まとまっている必要もありません。
実際、東大生たちが紙に書いている内容は、必ずしもきれいに整理された日記やノートではありません。
むしろ、メモのように断片的な言葉をつらねていたり、ただ「悔しい!」と大きく書いていたり、落書きに近い形で気持ちをぶつけている人もいます。
要するに、「きちんとまとめる」ことが目的ではないのです。
・「今日の英語の模試、リスニングが聞き取れなかった。焦りすぎた」
・「数学の大問3、最初の条件を見落としていた。なんで気づかなかった?」
・「理科は手応えあり。前日やった復習が出た!」
こうした記録を、数行でも、少しの文字数でもいいから、紙に残していく。その積み重ねが、内省を促し、頭の中を整理してくれるわけです。
「内省」する時間はどんどん減っている
デジタルが当たり前の現在、「内省」の時間はどんどん少なくなってしまっています。何か考えていても、スマホでLINEが来たらそちらに思考が奪われてしまいます。
歩きながら考えているとしても、大抵の場合は音楽を聴きながら、またはYouTubeを耳で聴きながら歩いていることも多いでしょう。このように、自分のことを内省する時間は減っていっているのです。
そしてここに、デジタルではなくアナログの紙のほうがいい理由があります。デジタル上で書こうとすると、内省しているときにそれを阻害する要因が発生することが多いです。通知がきたことで、そっちに意識が取られてしまったり、別のアプリをついいじってしまったり。だからこそ、そういうことのない紙のほうがいいわけですね。
多くの人は、「考えて書く」というイメージを持っていると思います。しかし実はこれは逆で、「書くことで考える」ということもあるのです。
手を動かし、文章を生み出すことで、思考ははじめて“輪郭”を持つ。だからこそ、東大生たちは紙の手帳に自分の思考を書き続けているのかもしれませんね。
記事をマイページに保存
できます。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら
印刷ページの表示はログインが必要です。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら

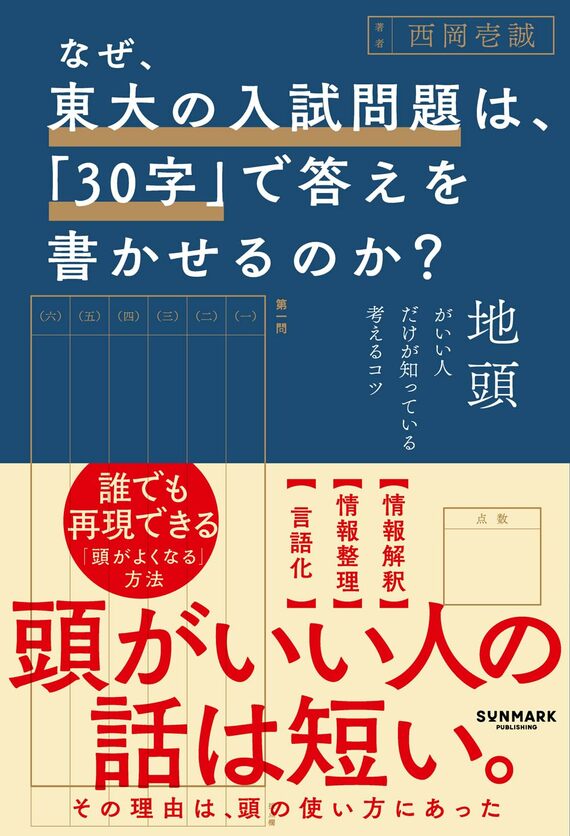






























無料会員登録はこちら
ログインはこちら