ロボット単独ではなく、ユーザーの一連の顧客体験や労働者の働きやすさの全体像を考えたうえで、つながりのあるDXの施策をおこなっています。そして各種報告書などを見ると、各担当役員それぞれがDXという言葉を使い、部門を超えて会社全体が連携していることがよくわかります。
2つ目のポイントは、データに基づいた導入ステップと活用ノウハウの蓄積です。
日々の運用で自律的に改善される
時系列で紹介したように、数カ月単位で活動がアップデートされ、各種の目標値が定量的に評価されています。仮説を評価項目に落としたうえで、何がうまくいき、何がうまくいかないのかという結果とそれに付随する導入ノウハウが着実に貯められていることが読み取れます。
結果として導入できない店舗についても条件がはっきりしてきていますし、上げ膳だけではなく下げ膳もという試みからもわかるように、日々の運用のなかで自律的に改善が回っていることも重要です。
デジタルは決して万能ではなく、お客さんに必要とされるサービスは何かを常に考え、気づき、行動できる人材を育てることが重要なのです。
そして、3つ目は現場を知り尽くした店長以上のインストラクター組織を構築していることです。
1つ目の経営層の戦略や2つ目のデータを踏まえた改善をつなぐ役割を持っているのがインストラクター組織です。
すかいらーくでは、店舗の経営も理解できる店長以上の従業員をロボット専任インストラクターとして最大17名で組織化し、ロボット導入全店舗に出向き、顧客・従業員の声をもとに改善活動を進めるようになっています。
多くのデータを取得し、リアルな効果や欠点も含めて理解したうえで、この時間帯はロボットを活用しましょうといったオペレーションの設計をすることができる組織になり、全店舗からの知見が蓄積されるのです。
彼らの活躍が日々更新されていくことで、一層ロボットの活用スキルが上がって、結果として経営への貢献ができるようになっているのです。
記事をマイページに保存
できます。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら
印刷ページの表示はログインが必要です。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら

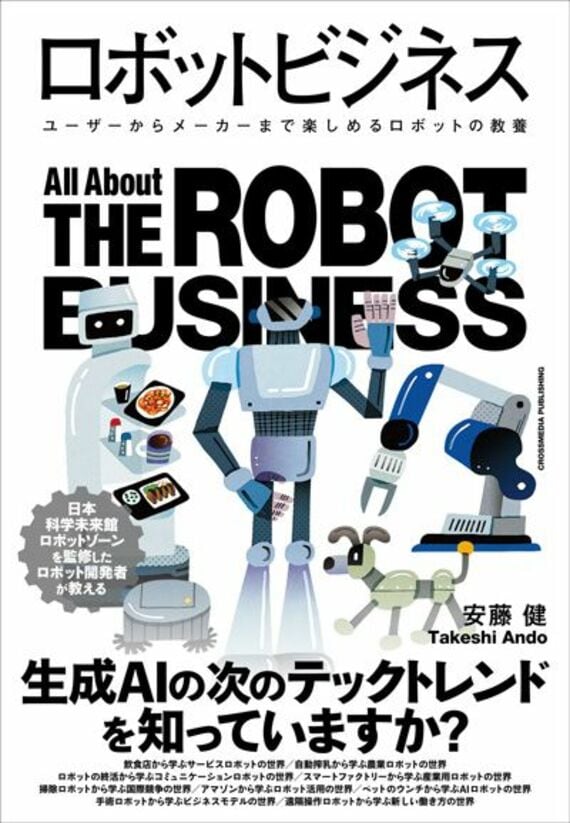






























無料会員登録はこちら
ログインはこちら