下水道事業は現在、深刻な資金難に直面している。その理由の1つは、老朽化した下水道管の更新に必要な予算が不足しており、その結果、多くの自治体では、必要な更新作業が遅れている。
本来、下水道事業は独立採算が原則であり、使用料で運営される。しかし実際には、多くの自治体が税金(一般会計)からの補助金に依存しており、事業全体の収支が黒字であっても、収益の約28.7%、設備投資の約17.1%が他の財源で補填されている。この構造は、自治体財政にとって不安定な要素となっている。
水道事業と下水道事業の圧倒的な違い
同じ水量を扱う場合でも、下水道事業は水道事業よりも圧倒的にコストがかかる。それは、下水道管は水道管よりも口径が大きく、埋設も深いことから掘削作業が大規模になるため工事費用が水道に比べて3〜4倍になることが1つ。下水の流れを維持するために複数のポンプが必要で、その設置費用と維持管理費も重い。
一方で、使用料収入が実際のコストに見合っていないケースが多く、料金の適正化が急務となっている。このままでは、全国の下水道事業が立ち行かなくなる可能性が高い。
そうなれば、自治体の財政基盤そのものが揺らぎ、最終的には市民生活に深刻な影響が及ぶことになる。国は自治体任せにせず、抜本的な対策を打つべきだ。
今回の事故は、単なる「道路の陥没事故」ではない。これは、全国各地で同じような事故が起こり得るという警告のサインである。今こそ、下水道の維持管理と更新投資に目を向けるべき時だ。「見えないから大丈夫」ではなく、見えないからこそ注意が必要である。
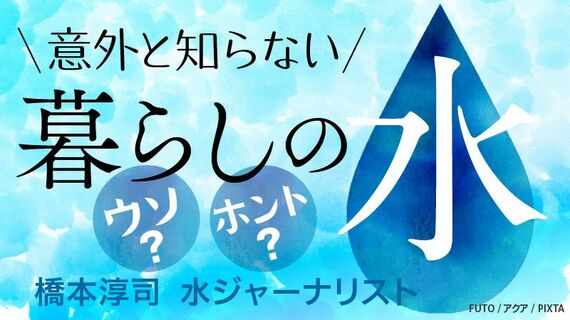
記事をマイページに保存
できます。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら
印刷ページの表示はログインが必要です。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら































無料会員登録はこちら
ログインはこちら