「Suica」が今のままでは生き残れない理由 10年計画で汎用的なスマホ決済サービスを標榜
このように私鉄や地方でタッチ決済が急速に広がる一方、JR東日本は「Suicaを軸にサービス拡張を図る」というスタンスを貫いている。
同社広報部は「SuicaやモバイルSuica、新幹線eチケットなどですでに一括利用の利便性を整えているため、当面はクレジットカードのタッチ決済を導入する予定はない」と明言する。
訪日外国人には「Welcome Suica」や「Welcome Suica Mobile」を拡張し、海外発行カードからのチャージをスムーズにしていくと説明する。Suicaという形で完結してもらうのが同社の強みという考えだ。
交通系決済の未来はどうなる?
JR東日本の新生Suica、私鉄各社のタッチ決済やQRコード乗車券――こうした動きが同時に進む背景には、磁気券や従来ICカードの保守コストや人手不足、インバウンド対応など、複数の課題が山積しているという現実がある。
それでも、「切符を買う」という行為が大きく減るのは確実な流れだろう。数年後には、「券売機で切符を買う」という文化が急速に廃れ、Suicaやクレジットカード、あるいはQRコードのいずれかをスマホやカードでかざすだけになるかもしれない。さらには、ウォークスルー改札が普及すれば、「何もかざさなくていい」時代が訪れる可能性もある。
こうした転換は、運賃収受の仕組みにとどまらず、“移動”そのものの概念を変えるかもしれない。たとえばサブスク型運賃やポイント還元、駅ビルや地元商店街との連動によるサービス展開など、クラウド化されたデータと決済基盤が連動することで、従来にはない利便性や料金体系が生み出されるだろう。
東京の通勤ラッシュを支えるFeliCaの高速処理は今後も活かされつつ、国際規格のタッチ決済やQRコードが併存していく日本の交通システム――10年後には、今とはまったく違う乗車風景が当たり前になっているかもしれない。
記事をマイページに保存
できます。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら
印刷ページの表示はログインが必要です。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら







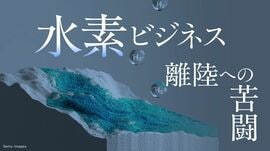





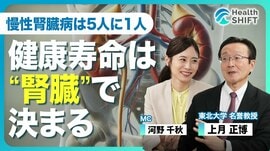

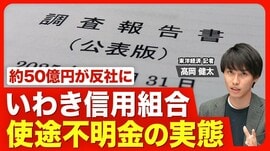
















無料会員登録はこちら
ログインはこちら