ドコモ通信網、進化する「24時間監視」の最前線 AI予兆検知で故障防ぐ、能登の教訓を活かす
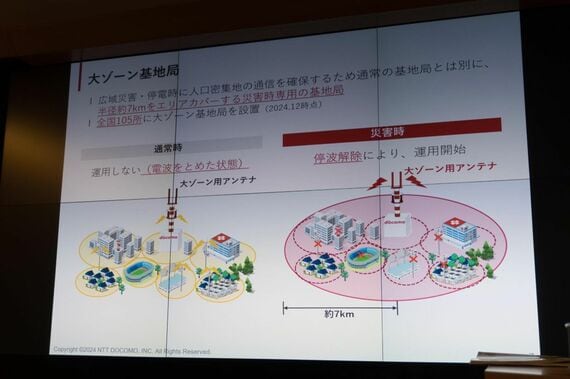

東京・大阪の2拠点体制も、災害時の重要なバックアップとなる。普段は東日本と西日本で分担しているが、一方の拠点に負荷が集中した場合は即座に業務を移管できる。さらに近年は、テレワークによる在宅監視も可能な体制を整備。コロナ禍での経験を生かし、有事の際の対応力を高めている。
能登半島地震が突きつけた課題
そんな最新鋭の監視体制は、2024年初めの能登半島地震で、想定を超える事態に直面することになった。
1月1日に発生した地震の影響は甚大だった。地震発生から3日後、停電の長期化による基地局バッテリーの枯渇も重なり、影響を受けた基地局は最大で260局に達した。平時を100とした場合のサービスエリアは30%程度まで低下した。
「被害の主因は停電と伝送路断でした」と、サービスオペレーション部災害対策室長の竹内宏司氏は振り返る。全体の38%が停電、35%が光ファイバーなどの通信回線(伝送路)の断絶、26%が両方の影響を受けた。基地局設備自体は長年の強靭化対策が功を奏し、物理的な被災は数%にとどまった。しかし、電力と通信回線の寸断に対する脆弱性が浮き彫りになった形だ。

特に深刻だったのが、陸路からのアクセスが困難な地域の復旧だった。道路の寸断に加え、余震や降雪も復旧作業の障害となった。ドコモは全国から技術者と機材を集結させ、のべ1万人体制での復旧にあたった。
能登半島地震では、新たな復旧手段も導入した。その一つが船上基地局。海底ケーブル敷設船「きずな」を活用し、輪島市沿岸部のエリア復旧を行った。船上基地局では同船にKDDIも設備を持ち込み、キャリアの垣根を越えた協力を行っている。また、輪島市の大沢地区では自衛隊のホバークラフトを活用して機材を搬送。陸路が寸断された地域でも、海からのアプローチで通信を確保した。

こうした多様な手段を駆使した結果、1月17日には立ち入り可能な地域の応急復旧を完了。3月1日には99%まで回復し、3月17日に完全復旧を果たした。ただし、「本来の伝送路が復旧するまでは、衛星回線などで応急的に対応している箇所もあります」と竹内室長は説明する。































無料会員登録はこちら
ログインはこちら