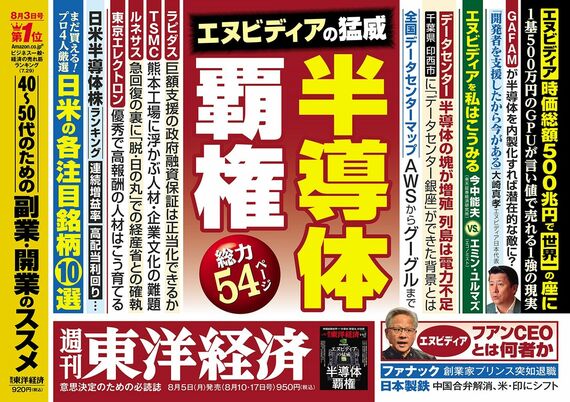エミン・ユルマズ「人工的な半導体バブルは危うい」 株価暴落前からAIブームに警鐘を鳴らしてきた
米司法省は6月、エヌビディアに対し反トラスト法(独占禁止法)違反の疑いで調査の準備を始めたと、ニューヨーク・タイムズなど大手メディアが報じた。
周知のように、かつてエヌビディアは同業の英アーム・ホールディングスを買収しようとしたものの、米連邦取引委員会(FTC)に差し止められて、結果的に買えなかったという過去がある。AI半導体でシェア約8割を握る王者について、米政府は懸念を感じているようだ。
本業においても、AI半導体を持っているのは今、エヌビディアほぼ1社しかいないが、今後はどうか。
1個1000ドルのコストでも3万ドル以上で売れた
現状、1個1000ドルのコストのチップを3万2000ドルで売っているのだが、顧客がいつまでもその高い値段で買うだろうか。米GAFAMは自社で半導体の内製化を進めているし、競合する米インテルやアームのほかに、中国企業も開発しようとしている。エヌビディア1強は10年間も20年間も続かない。
思えばエヌビディアは、かつての米シスコシステムズに似ている。
ネットワーク機器大手のシスコも、2000年のドットコムバブルでマイクロソフトの時価総額を抜いたが、同年にバブルがはじけて株価は10分の1に暴落してしまった。同様にAIも、機器や半導体などのハードがコモディティー(日用品)化したなら、栄えるのはソフト企業だろう。
生成AIはバブルで先に株価が上がっており、実態が本当に後で追いつくかどうかはわからない。AIがもたらす収益の危うさについて、米ゴールドマン・サックスや英フィナンシャル・タイムズも、リポートや紙面において警鐘を鳴らした。
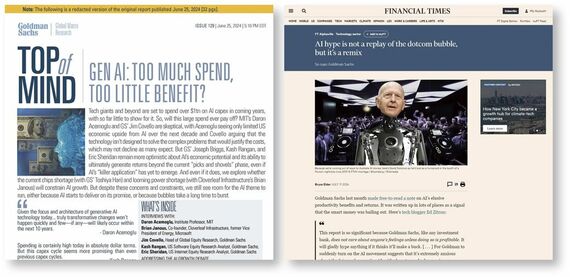
遅かれ早かれ、人工的な需要は崩落する。いつかAI半導体バブルも終焉を迎えるのではないだろうか。
記事をマイページに保存
できます。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら
印刷ページの表示はログインが必要です。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら