ユーロ圏諸国に対しIMFはあまりに甘い--ケネス・ロゴフ ハーバード大学教授
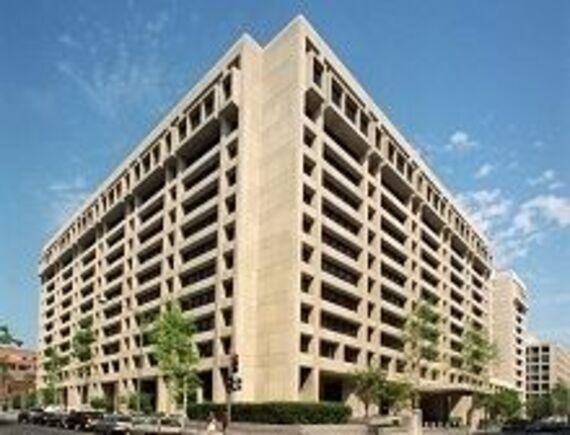
だから、普通の足早な景気回復がすぐそこまで来ていると思い込んだままの人が多い。だが、今回の金融危機で人々は、先進経済諸国と新興市場の区別は真っ赤な線で示されているわけではないとあらためて気づいたはずだ。バーナンキ米連邦準備制度理事会(FRB)議長は最近、「政治のマヒ状態が景気回復の主要な障害物になった可能性がある」と強く訴えた。しかし、新興市場の仕事に慣れているアナリストらは、金融危機後にこうしたマヒ状態を回避するのは非常に困難であると知っている。
新興市場のリサーチ担当者たちは、政策策定者の確約をそのまま信じるのではなく、当局の約束をはすに構えて受け止めることを学んできた。過誤が行われる可能性があるすべてのことについて、過誤が実にしばしば実際に行われてしまうのだ。IMFは、ユーロ圏の債務を持続可能に見せるためのこじつけを絶え間なく探すかわりに、現時点における債務の査定を疑うことにより注力すべきだ。
欧州以外の国でも、IMFは時の政権にあまりに多くの信用を長く与え、国家と国民の長期の利益を二の次にしてきた。IMFは、ユーロ圏周辺国の劇的な債務償却や中核国の債務保証の他国への再割り当てなど、より現実的な解決策を積極的に求めていない。
欧州の銀行の多くが非常に大きな資本不足を抱えていることを今やはっきりと認識したIMFは、ユーロ圏の債務危機に対する「包括的」かつ信頼に足る解決策を強く求めるべきだ。こうした解決策には、ユーロ圏の部分的な分割や根本的な憲法改正がかかわるだろう。欧州の将来、そして言うまでもなくIMFの将来がそれに懸かっている。
Kenneth Rogoff
1953年生まれ。80年マサチューセッツ工科大学で経済学博士号を取得。99年よりハーバード大学経済学部教授。国際金融分野の権威。2001~03年までIMFの経済担当顧問兼調査局長を務めた。チェスの天才としても名を馳せる。
(週刊東洋経済2011年10月8日号)
記事をマイページに保存
できます。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら
印刷ページの表示はログインが必要です。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら






























