ドコモが海外の携帯通信見本市で放った存在感 日本の通信事業者が「海外に販売」する時代が来た

この基地局は、半径数キロにわたって電波を放射して、通信可能な端末と無線通信を行う。この基地局の中で、アナログデータである無線をデジタルデータに変換して、次のRANにデジタルデータとして引き渡す。基地局の数は通信事業者によって異なるが、日本全国に展開している通信キャリアの場合は20万~30万の基地局を持っているというのが一般的だ。
RANは基地局から受け取ったデジタルデータを、コアと呼ばれる、通信事業者の局舎の中にある集中制御装置にわたす役目を果たしている。1つのRANで、2つや3つの基地局をカバーするので、基地局数の2分の1~3分の1のRANが全国に設置されている計算になる。
そしてコアは、例えばユーザー端末の契約情報などが格納されており、ユーザー端末から受け取ったデータをインターネット側に流していいのかなどの処理を行い、最終的にユーザーの端末がインターネットにアクセスすることを許可し、契約情報が適正でなければ通信を拒否する。このコアは、通信事業者の局舎に地域ごとにまとめて置かれ、日本全体で数カ所というのが一般的だ。
「ベンダーロックイン」に苦しめられていた
従来こうした、基地局、RAN、コアは、通信機器ベンダーが提供する専用機を使うのが一般的だった。エリクソン、ノキア、NEC、富士通、そして中国のファーウェイというのがそうした通信機器ベンダーの代表だ。3G時代には日欧のベンダーが強く、その後4G時代には中国のファーウェイが伸びたというのが通信業界の歴史だった。特にファーウェイは、基地局からRAN、コアまで非常に低コストで提供していったため、瞬く間にシェアを伸ばしていったというのが2010年代の歴史だ。
この時代に通信事業者がもっていた不満は「ベンダーロックイン」されているという点にあった。安定した通信環境を実現するためには、一度導入した通信機器は継続的に使わざるをえず、通信機器ベンダーの言い値の費用を払わされていた。
そんなときに日欧の通信機器ベンダーよりも安価なコストをひっさげて登場したのがファーウェイなどの中国勢だ。ファーウェイなどの中国勢は日欧の通信機器ベンダーとさほど変わらないクオリティーでありながら価格は安価で、日米欧の多くの通信キャリアで採用が進んでいった。
しかし、アメリカの中国デカップリング政策により、日米欧の通信事業者はファーウェイを選択できなくなり、再び日欧の通信機器ベンダーへの回帰が発生した。それが2010年代後半~2020年代前半に起こったことだ。

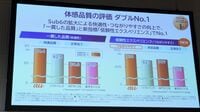





























無料会員登録はこちら
ログインはこちら