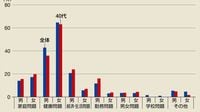田中:そうですね。白岩さんのエッセイを読んで、お父様を早くに亡くした喪失感や自分が父親になることが最初はよくわからなかったという感覚をすごくストレートに書かれているという印象を持ちました。そのことが今のお話に関連しているのかもしれません。
白岩さんが言うように、自分がそもそもどう育ってきたのかを語ってみる。それに対して社会が聞く耳を持つということは重要だと思います。
白岩:田中さんは、自分自身がどう育ってきたかをお子さんに語ることはありますか?
田中:上の子どもが大きくなってきて話すことが増えました。最近だと、息子が不利な条件で友達におもちゃを交換させられたという出来事があって、息子と「本当は交換したくないのに、だめだと言えないのは嫌だよね」という話をしたんです。
その時に「でも、パパも子どものころ同じようなことがあって、その時は嫌だって言えなかったよ」という話をしました。「嫌だと言えたほうがいいけれど、言えないこともあるよね」と。
アドバイスは、子どもの世界を無視してしまうことも
白岩:「(パパも)言えなかった」と子どもに伝えることが大切ですよね。僕も息子から「違う遊びがしたいのに友達から誘われて断れない」という話をされて。「断ったらいいよ」って言ったんですけど、実際に5歳(当時)の男の子がその子の生きている世界の中で断れるだろうかと考えた時に、無理だろうと思ったんです。友達と息子の関係性もわからないし。
だからその後で「断ったらいい、って言ったけど断れないこともあるよね。嫌だと思う気持ちはすごく大事だし、それは別に変えなくてもいいと思うよ」というふうには伝えたんですけど。大人の立場でアドバイスしてしまうと、子どもの世界を無視してしまうので、日々難しいなと思いますね。
田中:白岩さんのお話はまさに子どもの心に寄り添うというのはどういうことなのかを言い表していますね。
白岩:僕の場合、自分が男性として育つ中で経験した「バカとエロの大縄跳び」が本当に嫌だったという実体験があるんです。男子はみんなでバカなことをするとか、エロを受け入れるという強制参加の大縄跳びのようなものがあって、とにかくそこに入らないことには男の子として認められないという空気がありました。
僕は嫌だったけれど入らざるを得ないから、もう飛んだふりするみたいな感じでやってきたのですが、本当につらかった。息子がもしそういうことを好まなかった場合、自分と同じようにその中で生きていくしかないとしたらつらいと思うのですが、親にできることは限られていますよね。
息子が生まれて、自分と同じようにそういう男性としての生き方で悩んでほしくないと思ったことも『プリテンド・ファーザー』を書くきっかけのひとつになっています。