生前贈与、暦年課税と精算課税は組み合わせよ 相続前7年間に毎年110万円をどう贈与すべきか
(4)精算課税と暦年課税で年220万円まで併用可
今回の税制改正によって、精算課税にも年110万円の基礎控除ができる。精算課税と暦年課税を併用すれば、受贈者1人当たり年220万円まで贈与税は課されない。つまり精算課税と暦年課税をうまく組み合わせれば、より多くの贈与税を節税できる。
両課税方式とも非課税枠は110万円だ。ここでは3世代による最大非課税額のパターンを比べてみたい。
贈与の相手と方法を変えて組み合わせよ
実は税制改正後、精算課税と暦年課税をうまく組み合わせれば、より多くの贈与税を節税できる。両課税方式とも非課税枠は110万円。ここでは3世代による最大非課税額のパターンを比べてみたい。

【パターン①②】
受贈者である子が父母それぞれから精算課税で贈与を受ける場合、1つの課税方式につき受贈者1人の非課税枠は110万円が限度なので、父母から合計110万円までの贈与が非課税になる(父母からの配分は任意)。同様に、子が父母それぞれから暦年課税で贈与を受ける場合も、合計110万円が非課税になる限度である。
【パターン③④】
子および孫が父(祖父)から精算課税で贈与を受ける場合、非課税枠は子が110万円、孫が110万円である。同様に、子および孫が父(祖父)から暦年課税で贈与を受ける場合も、非課税枠は子が110万円、孫が110万円だ。
【パターン⑤⑥】
子が父母それぞれから贈与を受けるなど贈与者が複数いる場合には、精算課税と暦年課税の両課税方式を組み合わせることが有効になってくる。
例えば、子が父から精算課税、母から暦年課税による贈与を受ける場合、子は父からの贈与には精算課税の110万円、母からの贈与には暦年課税の110万円と、合計220万円まで非課税枠をフルに活用することができるのだ。同様に孫が祖父から精算課税、祖母から暦年課税で贈与を受ける場合、孫は合計220万円まで非課税になる。
【その他】
子の妻が父(義父)から贈与を受ける場合、子の妻は法定相続人ではないため、父の相続財産には加算されない、暦年課税による贈与が有利である。
なおこのケースでは、節税対策として生命保険の受取人として子の妻を指定すると、法定相続人と同様、贈与財産が相続財産への加算対象となるので、注意したいところだ。
いずれにせよ相続税や贈与税を賢く節税するには正しく理解することが必要だ。税理士などプロの専門家にも相談しながら取り組んでほしい。
記事をマイページに保存
できます。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら
印刷ページの表示はログインが必要です。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら

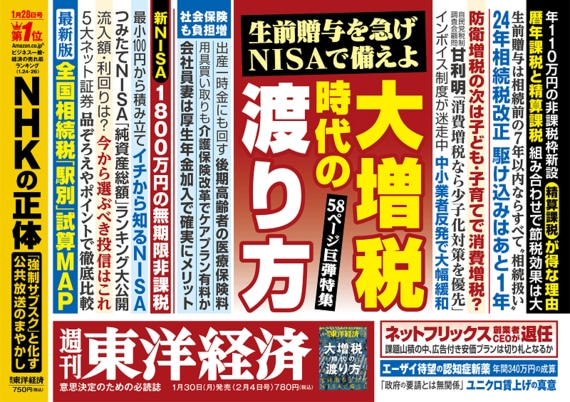






























無料会員登録はこちら
ログインはこちら