気候変動対策の国際交渉「COP」はもはや無意味だ 斎藤幸平・東京大学大学院准教授に聞く
――社会問題の傍観者になっていてはいけないということでしょうか。斎藤さんの近著『ぼくはウーバーで捻挫し、山でシカと闘い、水俣で泣いた』は、現場に出向いてさまざまな分野の当事者に話を聞き、学び、一緒に経験することの必要性を訴える内容ですね。
私はマルクスの研究を専門にしてきたが、理論だけでは足りない。この本では気候変動問題を含め、さまざまな社会問題をめぐる現場の実践について私自身が学び直す経験をつづった。取材を通じて多くの人たちがどんな苦難に直面しているかを考える機会を得た。
――著書では「脱プラスチック生活」にもチャレンジし、挫折した経験も書かれています。
プラスチックゼロを個人が徹底することはあまりにも大変で、無理だと認識した。プラスチックが含まれていない製品を探すことに労力を費やすよりも、地元の政治家に働き掛けたり、知り合いと勉強会を開催して解決方法を見出すことのほうが社会を変える力になるのではと感じた。
――そのために、どれだけの人たちの考え方が変わる必要がありますか。
『人新世の「資本論」』では、ハーバード大学の政治学者エリカ・チェノウェスらの研究を引用し、「3.5%」の人々が非暴力的な方法で本気で立ち上がると、社会が大きく変わる可能性があるということを書いた。独裁者を権力から引きずり下ろすのであれば、一時的な運動としてそのくらいの数の人たちが盛り上がれば、大きな力を発揮する。
私たちは自ら学び直す必要がある
もちろん、気候変動問題には少し違った側面がある。それは何かというと、持続可能な社会を作ることが目的である以上、もっと多くの人たちが積極的、かつ継続的に問題解決に取り組む必要があるということだ。つまり、ゴッホの絵にトマトスープをかけるだけでは、気候変動問題はまったく解決しないのだ。
その点では3.5%の人たちが出すメッセージからもっと多くの人たちが学び、自らの価値観や生活を変えていく必要がある。だからこそ、私自身を含めたマジョリティが他者から学び、変わることの大切さを今回の本で訴えた。




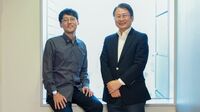


























無料会員登録はこちら
ログインはこちら