そもそも営業と製造との間でしっかりとした情報共有がされておらず、トラブルが発生すると古参幹部同士が双方に責任のなすり合いをしてけんか腰になってしまうケースも見受けられます。
そこで経営者は、次に研修制度などを導入して古参幹部らに改めてマネジメントやリーダーシップを学んでもらうための機会を与えようとします。しかし幹部たちは真剣にマネジメントを学ぼうとはしないため、残念ながらこの方策も多くの場合は失敗します。
あるいは突然、若手を幹部に登用したり、インセンティブの強い評価制度を導入して、その評価制度に合わせてかなりドラスティックに人事を動かそうとするケースもあります。しかし、組織づくりに焦れば焦るほど「殿のご乱心」と従業員の不安は大きくなります。次第に従業員の間に、この会社は大丈夫だろうか?という不安感が増していくだけで決していい方向には向かわないのです。このように、古参幹部の人事ばかりにとらわれていると、組織の中はガタガタになっていってしまいます。
公平バイアスに陥らない
また、全体の底上げをしようと考えたり、全員に公平にチャンスの場を与えようと、社員全員に研修を受けさせようと考えてしまいがちです。しかし、あまりやる気のない人、成長したいと思わない人も対象に含めて研修を行っても効果は上がりません。
組織改革の初期段階において、最も重要なのは「絶対に失敗しない」ことです。つまり、成果の上がりそうな人、成長が見込める人だけに絞って研修を受けさせることが肝心ということです。
企業は過去のためにあるのではなく、未来のために存在しています。旧来の方針を継続するのではなく、新たな方針で組織づくりや経営をしていくことでしか、企業を発展させていくことはできません。そうである以上、新たな方針に賛同できない幹部や従業員は、組織にとっては将来の大きな足かせになります。
新方針に共感する人材を登用し、評価し、そうでない人は適切かつ少しずつ代謝させていくことが組織づくりの要となります。
記事をマイページに保存
できます。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら
印刷ページの表示はログインが必要です。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら

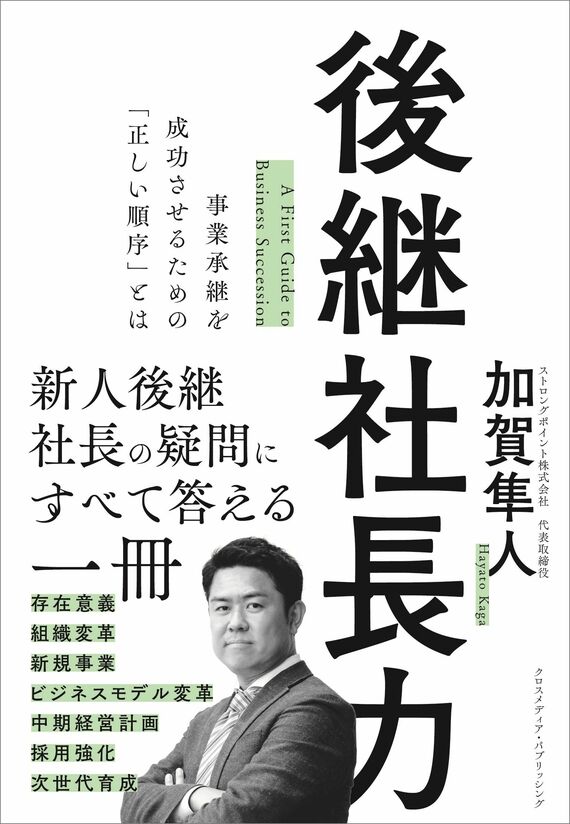






























無料会員登録はこちら
ログインはこちら