
特集「"移民”解禁、ニッポン経済浮沈の岐路」の他の記事を読む
去る12月8日、出入国管理法改正案が参議院で可決、成立した。4月には省令なども整い施行されることだろうが、野党の大部分は「審議時間が短い」と反対、事実上の強行採決になった。
国会での審議に時間をかければいい法案ができるとは限らない。政治ではタイミングも大切だ。
終戦直後に学校制度の改革が議論されたとき、私は小学校5年生だった。もしあの改革が長い議論で施行が2年も延期されていたら、私は奈良県の村営高等小学校に進み、村役場か農業協同組合に勤めて生涯を終えたかもしれない。
改革議論を繰り返す官僚や国会議員にとっては、2年や3年は何ということもないだろうが、その制度の適用を受ける人にとっては12歳のときは一生に1回、そのときに施行されていた制度によって人生が左右されることもある。
今、日本は「人口減少の瀬戸際」。ここでよき「未来志向の体制」が採れるか、小さなことにこだわって大局を見失うかは、それこそ日本の未来を決める重大問題である。
深刻化する日本の人口減少
日本の長期展望を考える場合、最大の問題は「人口減少」である。
日本は終戦直後の1947年から51年にかけて大量の出産があった。戦地や兵営に閉じ込められていた若い男性が故郷に帰り、待ちわびた女性と結婚して子をつくったのだ。あの終戦直後の混乱の中で、正式に結婚して多くの子を生み、戸籍に登録して小中学校に通わせたのは、「民族の偉業」というべきだろう。後に私が「団塊の世代」と名付けた人口の塊である。
だがその後は、産児制限思想が広まり、日本の出生数は急減する。当時の厚生省などの専門家は、「人口減少は一時のこと、今に47〜51年生まれの『団塊の世代』が出産適齢期を迎え、日本は再びベビーブームになる。日本の問題は依然として『人余り、土地不足』だ」と言い続けていた。政府の各省もこれを信じ、各地の農地造成や山間部への道路建設で可住地の拡大に何兆円もの投資をしていった。
幸か不幸か、この予測は72〜73年には的中、第2次ベビーブームを生んだ。
しかし、この時期の出生数の増加が厚生官僚の言うような「親の数が多いから生まれる子の数も多い」という単純なものだったのか、日本万国博覧会の開催によって振りまかれた陽気な雰囲気のせいだったのかはまじめに解明されなかった。
その結果、「日本には25年か30年に1回ベビーブームの波が押し寄せる」という神話が定着した。官僚たちがまき散らした「人口過多警戒論」である。
だが、第2次ベビーブームから25〜30年経った20世紀末、第3次ベビーブームは生じなかった。その頃日本の出生率は1.3前後まで下がり、世界的に見ても「極めて低い水準」になってしまった。「団塊ジュニア(団塊の世代の子どもたち)は生まれたが、団塊サード(団塊の世代の孫たち)は生まれなかった」のだ。
本来ならそれに気づいた段階で少子化対策に強烈な手を打つべきだったろう。だが当時の日本は、政権の交代やバブル景気崩壊後の不況など目前の問題に忙しく、長い先の少子化問題にまでは手が回らなかった。
人口減少社会への適切な対処法とは
20世紀末に「人口波動予測」が間違いだったことがわかっても、この国の政治家や官僚は、人口対策には積極的には動かなかった。担当の厚生労働省は高齢者対策に忙しく、出生率の問題を真剣に取り上げなかった。
これまでの日本は、外国人を「労働力」としてのみ考え、「次世代の日本人をつくる人材」とは考えなかった。その根底には、「日本はヒト余り、土地不足の国」との思い込みがある。
同時に、この国には太平洋戦争前の「産めよ、殖やせよ、皇国の民」の記憶が大きなトラウマになっていた。「子を生むか生まぬかは個人の自由、社会的圧力で左右すべきでない」との思想も強かった。











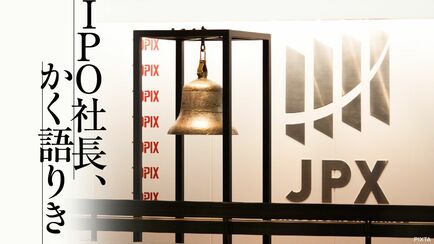























無料会員登録はこちら
ログインはこちら