吉川 洋 立正大学教授

今の経済学は現実と大きく乖離してしまった。経済学に携わってきた者として、大変に残念。しかもその乖離はますます広がっているように思える。
以前であれば、マクロ経済学とはケインズ経済学のことであり、ミクロ経済学とは新古典派が唱えた均衡理論(価格は需要と供給が一致するように市場で調整されるとする理論)を指していた。
資本主義経済は時として不況に陥る。そのときは供給よりも需要が不足しているから、裁量的な財政・金融政策によって対処する。ケインズ経済学の出番だ。そして完全雇用が実現したら、効率的な資源配分が重要になる。そこでは新古典派の均衡理論を使う。つまり経済学は、マクロとミクロの二刀流だったのだ。
ところが1970年代以降、特に私の専門とするマクロ経済学が大きく変わった。一言でいえば、“マクロのミクロ化”だ。ケインズ経済学は完全に忘れ去られた。今の主流派経済学は「国全体のことなど考える必要はない。あるのはミクロの問題だけだ」と声高に主張しているように見える。

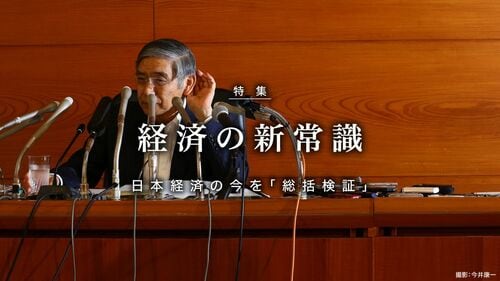































無料会員登録はこちら
ログインはこちら