エヴァを理解するために必要な「オタク」の概念史 作り手の葛藤と視聴者のそれが同時代的に共鳴
宮﨑事件が起こってからは、『毎日新聞』1989年8月20日はじめ、「おたく」と「ロリコン」「死体愛好」「ホラー」などが結びつき、「不気味」「異常」などと否定的に表現されることが急増していく。
『新世紀エヴァンゲリオン』の企画が構想されたのは、このような「オタク」像が社会的に定着して間もない時期でもあった。繰り返すが、「オタク」はまだ社会的に認められていないし、アイデンティティとしてもうまく機能していない時期である。その頃には「オタクでいてもいいのだろうか」「自分とは何なのだろうか」という悩みは、当時者たちに発生しやすかった。
庵野秀明自身の「オタク」観も紹介しよう。妻である安野モヨコが、2人の夫婦生活をモデルに描いたエッセイ漫画『監督不行届』(2005)の巻末インタビューで庵野は、「僕がオタク」と断ったうえ「いわゆるオタクの内包的特徴」を挙げていく。
エヴァの中で比較的に検討される「オタク」の類型
「内向的でコミュニケーション不全、つまり他者との距離感が適切につかめないとか、自己の情報量や知識量がアイデンティティを支えているとか、執着心がすごいとか、独善的で自己保全のため排他的だとか、会話が一方的で自分の話しかできないとか、 意識過剰で自分の尺度でしか物事をはかれないとか、ナルシスト好きだとか、肥大化した自己からなりきり好きであこがれの対象と同一化したがるとか、攻撃されると脆い等々」(p141-142)。
これが『新世紀エヴァンゲリオン』という作品の中で批判的に検討される「オタク」の類型と見ていい。
ここで指摘されている内容は、正直、耳が痛い。隠すつもりもないが、筆者自身もそういう性質を持っており、この意味での「オタク」にとても当てはまるのだ。
本書の言う「オタクの実存の物語」とは、このようなアイデンティティの動揺と不安の中で、自己を批判したり肯定したりして確立を手探りしていく営みのことである。庵野秀明を含む作り手たちの葛藤と、視聴者たちのそれが同時代的に共鳴し、オタクという新しい生き方が一般化してきた日本社会をどう捉えるべきかという大きな議論とも同調していったのだ。
記事をマイページに保存
できます。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら
印刷ページの表示はログインが必要です。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら

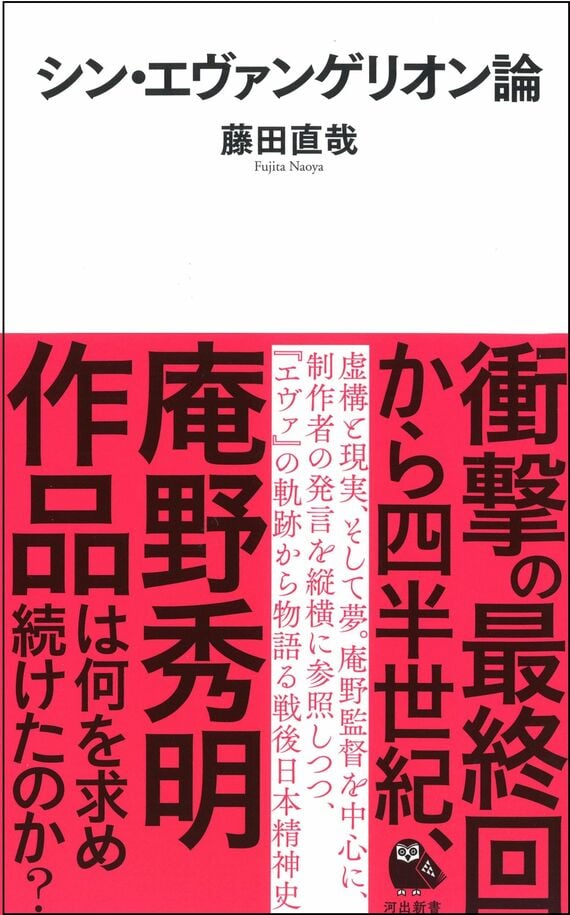






























無料会員登録はこちら
ログインはこちら