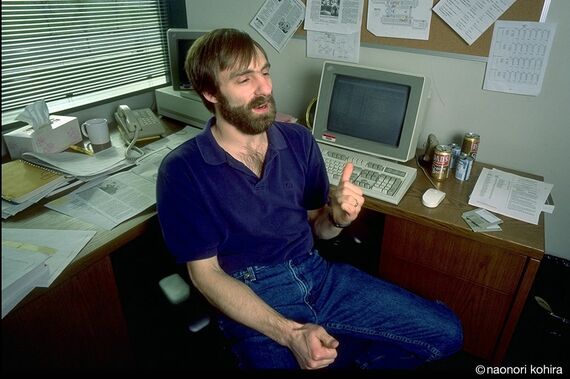
しかし彼が人とテクノロジーの接点に着目したことは確かであり、だからこそパーソナル・コンピューターというコンセプトを考えたとき、何よりも重視したのはユーザー・インターフェースだった。加えてそこに「友だち」という視点を持ち込んだ。ジョブズにとってパーソナルなコンピューターとは、機能的にもデザイン面でも「フレンドリー」なものでなければならなかった。
例えばビル・ゲイツのマイクロソフトに「友だち」という発想はまったくない。彼らが相手にしているのは無人格的な顧客であり、企業や法人である。一方、友をもてなすという態度で個人にアクセスすることを考えたのはアップルであり、とりわけジョブズである。
個人の心にアクセスできるのは「シンク・ディファレント」のような魅力的な物語であり、デザインという美である。ジョブズには両方の才能があった。そして物語と美を首尾よくビジネスに結び付けることができた。つまり彼のビジネス感覚は最初から個人へ向かうものだったと言える。
ジョブズが製品の種類を増やしたくなかった訳
だからジョブズにとって、自分たちが送り出す製品はただ売れればいいというものではない。本心から「友だち」に勧められるものでなければならない。
アップルが製品の種類を増やすことに、ジョブズは一貫して反対したと言われる。大切な「友だち」に届ける製品が、そんなに何種類も作れるわけがないということだろう。どの製品も自分(たち)が精魂を込めて作ったものでなければならない。販売店のニーズにあわせて作るようなものであってはならない。
おそらくゲイツはそんなことは考えないだろう。彼にとって製品の種類はいくら多くてもいい。むしろハードウェアの選択肢は多いほどいい。現にIBMのPC互換機の登場をきっかけに、デルをはじめとするさまざまなハードウェア・メーカーが製造に乗り出し、パーソナル・コンピューターはあっという間にコモディティー化してしまう。
これらのメーカーにオペレーティング・システムを積極的にライセンスすることで、ウィンドウズは一時期90%以上のシェアを占める。市場シェアの拡大だけを念頭に置けば、ジョブズのやり方は必ずしも正しいとは言えないのだ。
にもかかわらず、ジョブズはかたくななまでに製品の細かなデザインや機能や仕様にこだわる。『消えた少年たち』のスティーヴィは、いくら親たちに注意されてもコンピューター・ゲームをやめようとしない。スティーヴィにとってコンピューター・ゲームは友だちとつながる唯一のツールなのだ。ジョブズのかたくなさも、スティーヴィの場合と似ているかもしれない。
僕たちのスティーブにとっては、自分(たち)が作る製品は「友だち」とつながるための大切なツールである。決してコモディティー化していくようなものであってはならないのだ。
































