専門家と素人の断絶、あるいは、たこつぼ化ということについて一例を挙げてみよう。ポアンカレ予想という未解決だった数学の難問が、100年近い時を経て2002年にロシアの数学者グリゴリー・ペレルマンによって証明された。このニュースで驚かされたのは、世界中の権威ある数学者たちがペレルマンの証明の正しさを確認するまでに実に4年もの時間を要したというのである。
つまり、現代における専門知の中には、その分野の専門家同士ですら十分に理解することが容易でないものもある。逆にいえば、専門家であっても、その専門知を発揮できる分野は意外なほど狭く限定されている。ましてや素人がその内容を直接理解することはほぼ不可能に近い。
そういったことを踏まえて、専門知に関する1つ目の問題、「民主主義社会において、素人が専門的な知識を必要とする分野について、政策決定を行うことができるのか?」を考えなくてはならない。
「対話型専門知」を持つ人々が政策決定に関与
専門知というもの自体について研究する学問分野もあり、最も広い言い方をすれば「科学哲学」である。
科学哲学における最近の研究によると、論文を作成するなどして実際にその研究分野の進展に貢献することのできる人の持つ知識を「貢献型専門知」と言う。そして、論文発表などの成果を生み出すわけではないが、その分野での専門知を十分に理解し、貢献型専門知を扱う専門家と対等にコミュニケーションのできる能力を「対話型専門知」と言う。
対話型専門知を持つ人たちは、専門家と素人の間を取り持つ「通訳」のような役割を果たすことができる。こういう人たちの存在によって、素人によって構成される一般社会、あるいは政治家や官僚などの政策を決定する立場の人たちは、専門知を社会の中に取り込み活用していくことが可能になる(H・コリンズ、R・エヴァンズ『専門知を再考する』)。
この対話型専門知を持つ人たちが、政策決定のプロセスに適切に関与していくことによって、専門家と素人の断絶を埋めていき、さまざまな誤った政策決定を回避できるというのが、一つの希望的観測ではある。
しかし、あくまでも「希望的」としか言えないのは、対話型専門知を持つ人が、その「能力」をどのように使用するかは、あくまでも彼ら個々人の意思によるためである。

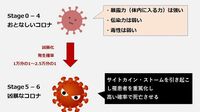
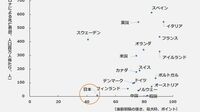




























無料会員登録はこちら
ログインはこちら