26歳で逝った五輪選手を戦争に駆り立てたもの 1940年「幻の東京大会」五輪は一体誰のものか
いま私たちは新型コロナウイルスという、戦争とは違った試練に直面している。
緊急事態宣言発令後の3カ月を経て、アスリートの中に変化が生じてきた。閉塞感漂う社会のためにスポーツを通じて自分にできることは何か、自らの存在意義を問い始めているのだ。SNSで将来アスリートを目指す子どもたちのために、究極の技を伝えようと発信するアスリートもいれば、ステイホームでのトレーニングを紹介し、多くの人々にスポーツの楽しさを伝えようという選手も現れている。
そうした発信者の1人が、鈴木聞多の後輩となる陸上短距離のエース・桐生祥秀選手だ。彼は緊急事態宣言中、自分について深く内省する時間を持てたという。そのうえで、東京オリンピックが自分にとってどんなものになったのか、NHKスペシャル「TOKYOアスリート」(7月18日放送)の中でこう語っている。
「これだけのことに情熱を注げたんだから」
「1個の目標だったら1個崩れたら目標が全部終わっちゃうの、悲しいじゃないですか。だから、いっぱい目標を持っています。このまま陸上選手の俺が終わったとしても、これだけのことに情熱を注げたんだから、これからの将来も数個情熱を注げることがあると思う。別に東京(五輪)がどうなろうと変わらないことなので、目標があるのでそこはブレない」
そして桐生選手は言う。「みんなを笑顔にできたり楽しませたりする情熱が湧くのがスポーツ」だと。その力を信じて彼は走り続けるのだ。
今回の延期が、これまでのオリンピックの「ありよう」を変える契機となるのかもしれない。いま「不要不急であるスポーツを楽しむときではない」と、東京オリンピック・パラリンピックに否定的なムードが漂い始めているが、私はそうは思わない。
新型コロナウイルスが、人々を分断し引き裂こうとしているいまこそ、スポーツそしてオリンピック・パラリンピックは人々の心をつなぎ1つにするものになるのではないだろうか。80年前のアスリート、そして現代のアスリートたちがその意義を訴えているように思えてならない。
記事をマイページに保存
できます。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら
印刷ページの表示はログインが必要です。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら

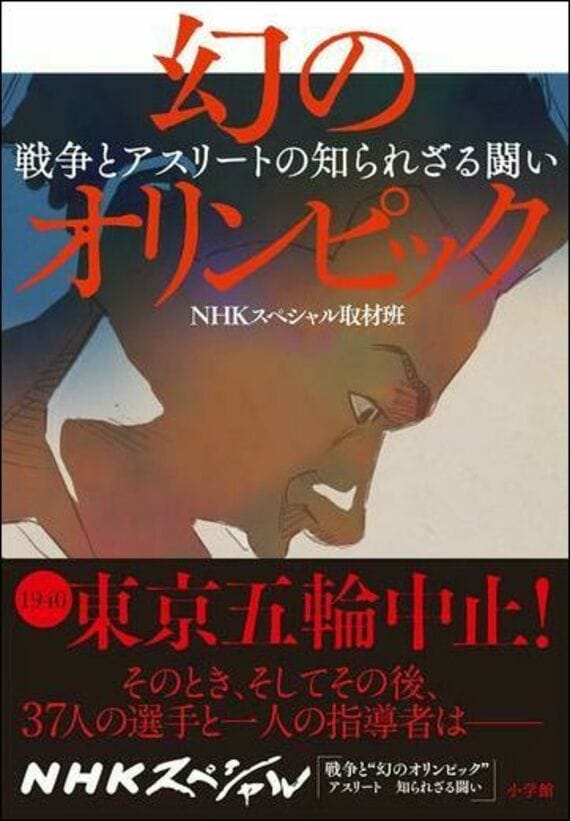

































無料会員登録はこちら
ログインはこちら