コロナ危機に下村治が再評価されるべき理由 独自の成長理論を生んだ希代のエコノミスト
さて、1960年代の高度成長を的確に予言した下村であるが、1970年代に入ると一転して、低成長を唱えるようになる。下村の診断では、当時の日本は、先進工業国からの技術導入によって生産性を上げるという段階を過ぎていた。
「長期停滞」論と1970年代の下村治
そうなると、1960年代のように、旺盛な民間設備投資が主導して経済が活性化し、購買力も増大するという形の成長は望めなくなる。生産能力に見合うだけの国内需要が生まれなくなり、需要不足による不況か、輸出超過となるであろう。「これがつまり、これまで民間主導の経済であったものが、これからは政府主導、財政主導の経済に変わらざるをえないということの本質である」と下村は主張した。
成熟した低成長経済では、積極的な財政政策による政府主導の経済にならざるをえない。これもまた、実に今日的な洞察である。アメリカの著名な経済学者ローレンス・サマーズは、21世紀の経済が低成長・低金利の「長期停滞」状態にあると主張している。
そのサマーズも、長期停滞下では、財政政策が最も重要になると論じているのである。
1970年代初頭、国債発行による財政支出の拡大と減税を主張した下村に対しては、またしても「そんなことをしたらインフレを招く」という批判があったようである。下村は、そういう批判は、戦時中と平時の経済を混同するものだと一蹴した。戦時中の財政支出の拡大は、確かに高インフレを招いた。
しかし、平時の日本では十分な生産能力があるので、インフレにはなりえないのだ(ちなみに、1970年代はインフレが大きな問題となったが、その主な原因は、石油危機による原油価格の高騰であって、財政赤字のせいとは言えない)。
このように下村は、インフレを決定するのは「生産能力と需要との相互関係」であるという基本を終生、手放さなかった。需要が拡大して、それに見合う生産能力も拡大する。これが、経済成長である。
ところが、今日の経済学者たちは、この「生産能力と需要との相互関係」という基本すら見失い、単に政府債務が増えたというだけで、「ハイパー・インフレになる」などと騒ぎ立ててきた。長期のデフレであるにもかかわらずだ。日本経済が成長を止めてしまったのも当然であろう。しかも、こうした経済学者たちは、戦後最悪といわれるコロナ危機に直面してもなお、財政赤字を懸念している始末である。
今ほど、下村治が求められている時はない。
記事をマイページに保存
できます。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら
印刷ページの表示はログインが必要です。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら

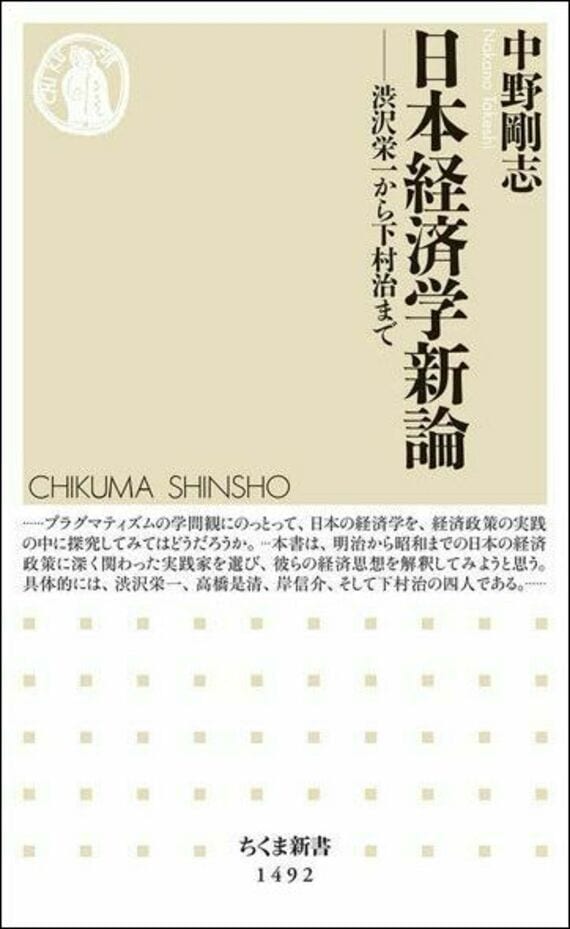































無料会員登録はこちら
ログインはこちら