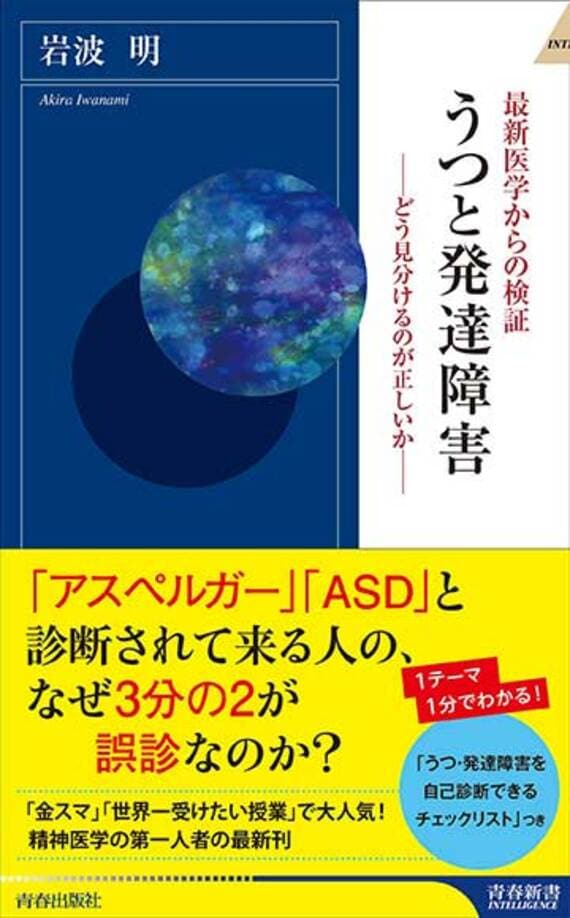「うつの人に頑張れはNG」と言い切れない理由 前向きな言葉が「回復」を促す場合も
休職からの社会復帰を目指すのであれば、少しずつ復帰に向けたリハビリ(リワーク)を進めることが重要になります。このような時期においては、多少気分が乗らなくても、頑張る必要があるでしょう。
私も、職場への社会復帰を目指している人に「図書館で半日以上過ごしてみましょう」などと指導することがあります。そのためには、休養優先でルーズになっていた生活習慣を改め、自分を律し、しかるべき時間に起床して身支度を整え、出かけないといけません。
これは健康な方なら難なくこなせることですが、うつ病によるブランクが長いと、これだけのことでも難しいのです。それでも、回復を目指すならば、本人なりの努力がどうしても必要になります。また軽症のうつ病なら、行動し動くことで、さらに改善することもあるのです。
「頑張れ」が有効な場合もある
前の項目で述べた「頑張れと言ってはいけない」という言葉が、金科玉条のように広まったのは、時代的な背景があったのかもしれません。
以前は、社会的にうつ病の理解はなかなか進んでいませんでした。そのために「うつ病なのにそう認識されない人」が数多く存在していました。仕事をしていてもはかどらない、元気がない。しかし、周りは病気のせいだとは思いもよらないのです。だから悪気なく「もっと頑張れ」という言葉を口にしてしまい、それがうつ病患者を追い詰め、無理をさせていました。
その後、うつ病が社会的にクローズアップされるようになり、「頑張れと言ってはいけない」がわかりやすかったこともあり、一般に広く伝わったと考えられます。
前述のとおり、うつ病の回復状態によっては、「頑張れ」と患者の背中を押してあげたほうが、より回復が進みます。例えば「ここまでできないと、次の段階には進めませんよ」と示してあげることは重要です。
とはいえ、無理は禁物です。「ここまでなら、無理なく頑張れるだろう」という一線を、医師は見極めなければなりません。不安感や憂鬱感がどの程度かも重要です。さらに、注意しなければならないのは、「抑制」の症状です。
抑制とは、「頭が働かない、判断力が鈍る、根気がない」といった症状です。憂鬱さは「なんとなく元気がなさそう」「表情が暗い」といった形でわかりやすいですが、抑制の症状は表に表れにくいのです。
抑制の症状がどれだけ回復しているのか、慎重に様子をうかがう必要があります。回復しているように見えても、実はまだ集中力が回復していないため、仕事に必要な文書をしっかり読むことができないケースもあるのです。
治療においては、うつ病からの復職を受け入れる側との連携も必要になります。
上司がすべてを把握することは難しいと思いますが、環境が整っている会社であれば、人事部や産業医、あるいは保健管理センターなどが復職や復帰の仕方について対応してくれるでしょう。本人、病院、職場が連携しながら、復職を目指していくのが理想です。
記事をマイページに保存
できます。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら
印刷ページの表示はログインが必要です。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら