赤羽vs立川「人気急上昇駅」の意外な共通点 現在の住宅街や公園はかつて「軍用地」だった

国の動きに連動して、民間の飛行機メーカーも続々と立川に集結した。石川島飛行機製作所は1930年に工場を立川に移転。1936年には、立川飛行機と改組した。
航空産業が集積したことにより、立川は工業都市となり経済的にも活況を呈した。いつの頃からか、立川は“空都”と呼ばれるようになる。
空都として隆盛を誇った立川だったが、敗戦により暗転。立川の軍用地はGHQに接収された。駅前の広大な敷地は、1977年の全面返還までアメリカ軍の基地および後方支援施設が並んでいた。
全面返還後、立川駅前の大部分を占める国有地は国の出先機関や公共施設が立地されたほか、国営昭和記念公園に転換された。また、一部は民間に払い下げられたものの、一画が大きすぎたことから個人用住宅として分譲されることはなく、大資本へと売却された。
しかし、立川駅前の土地が民間に払い下げられた後も立川駅前の開発は遅々として進まなかった。立川駅前の発展を阻害していた要因は、市街化調整区域という都市計画法の壁だった。
都市計画法は、開発を促進する市街化区域と開発を抑制する市街化調整区域とを線引きしている。こうした線引きがなされる理由は、無制限に開発を許可してしまうと、無計画な都市がつくられてしまい、上下水道や道路をはじめとするインフラ未整備の街ができてしまうからだ。市街化調整区域だったこともあり、立川駅の一帯は長らく不遇をかこった。
多摩都市モノレールの設立により状況が一変
しかし1986年に多摩都市モノレールの運営会社が設立されると、状況は一変する。商業施設や高層マンションが建設できるようになり、広大な空地には次々と開発計画が浮上した。
立川の軍都化の一翼を担った立川飛行機は、戦後に製造業部門と不動産部門を分離。名称も立飛企業と改めているが、その立飛企業が立川駅前の開発を主導した。
2015年には三井不動産とタッグを組んで大型商業施設「ららぽーと立川立飛」を開業。2017年には、プロバスケットボールの本拠地「アリーナ立川立飛」をオープンさせた。アリーナ立川立飛はバスケットボールの試合だけではなく、大相撲巡業なども開催されており、立川市民のみならず市外からも人が集まる。
こうしたことから、立川駅は三多摩でも屈指の繁華街と化した。発展著しい立川駅だが、前述した歴史をたどったことからも住宅地が少ないことが課題として残る。立川市の人口は約18万人。立川市よりも都心から離れている八王子市の人口は約57万人、同じく町田市の人口は約43万と、人口面で後塵を拝したままだ。
市の人口がそのまま駅の勢いに直結するわけではないが、それでも市の人口が玄関駅に与える影響は大きい。軍都として発展した赤羽駅と立川駅。両者はともに交通の要衝というアドバンテージを得ている。今後、街の発展は鉄道網を生かせるかどうかにかかっている。
記事をマイページに保存
できます。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら
印刷ページの表示はログインが必要です。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら

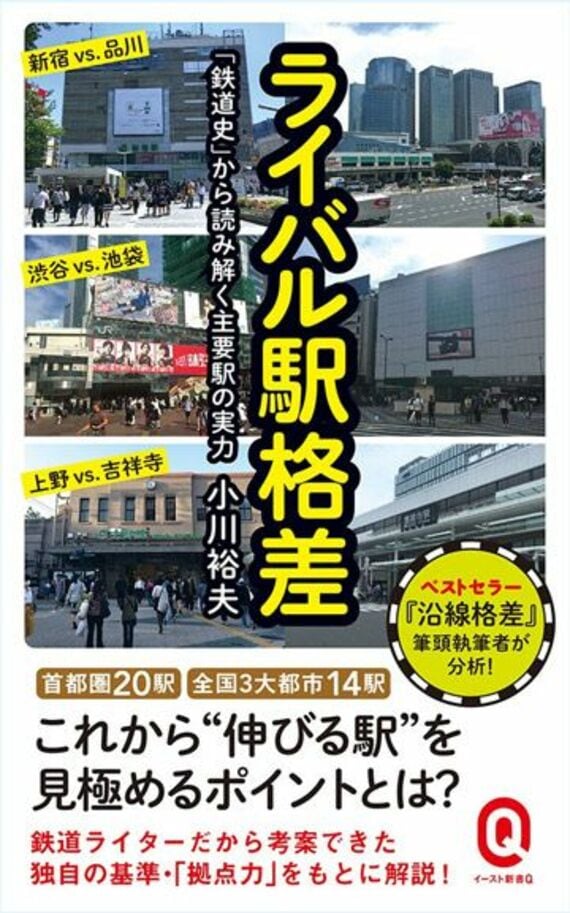






























無料会員登録はこちら
ログインはこちら