ブルー・オーシャン戦略の知られざる本質 革新もいずれはマネされ競争にさらされる
映画『グレイテスト・ショーマン』で描かれたように、P.T.バーナムが始めたサーカスも当初は熱狂的に受け入れられ、よそにはないイノベーションであったことは間違いなく、そのサーカス団が100年以上続いたことも驚異的と言える。しかし、ある時点でのイノベーションが永遠に続くことはない。ブルー・オーシャンもいつかはレッド・オーシャンになる。そのようなコモディティ化を防ぐか、あるいは新たなブルー・オーシャンを創造する必要がある。
投資の神様と呼ばれるアメリカの投資家バフェットは成長企業へ投資することで莫大な財産を築いたが、銘柄選びの基準として「参入障壁」の存在を挙げる。どんなに優れたビジネスモデルも簡単にマネができてしまうのではすぐに真っ赤に染まってしまう。
他社が切り開いたマーケットであってもそこが有望であれば多くの企業が押し寄せることを止めることはできない。したがって参入障壁が高ければ高いほど、長期間にわたって大きな利益を上げることができる。参入障壁はブランド力、技術力、特許、規制など、さまざまなものが考えられるだろう。
ブルー・オーシャンと孫子の共通点
従来の経営戦略はライバル企業と戦って勝つことに主眼が置かれており、そういった意味でブルー・オーシャンは奇抜・異端な戦略かのように見られているフシもある。しかしそれもまた誤解だと言える。
戦略論の元祖ともいえる孫子の兵法では「兵は詭道(きどう)なり」と説かれている。詭道、つまり戦いにおいては敵を欺き、だませという意味だ。真正面からの価格競争、消耗戦は孫子が書かれたとされる紀元前500年の時点ですでにヘタクソな戦い方であると指摘されていた。
そして孫子の兵法では「百戦百勝は最高の状態ではない、戦わずして勝つのが最高である」とも説かれている。たとえ戦いに勝ったとしても無傷では済まない。ビジネスに置き換えれば、消耗戦で勝ち残ってもそれは薄利多売で自社もライバルも薄い利益を互いに削り取るような戦いを繰り広げた結果かもしれない。最高の勝ち方は戦わずして勝つことである……これはブルー・オーシャン戦略の発想と一致する。
紀元前に説かれた戦略と21世紀に提唱された経営戦略がくしくも一致することは決して偶然ではない。ブルー・オーシャン戦略は現代の奇抜な戦略ではなく、一過性のはやりでもなく、王道の経営戦略であるという視点で改めて学んでみることをお勧めしたい。
記事をマイページに保存
できます。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら
印刷ページの表示はログインが必要です。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら



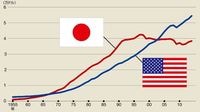



























無料会員登録はこちら
ログインはこちら