福永さんが生まれたのは1967年8月の愛知県。腕のいい左官職人の父とそれを支える母、歳の近い姉がいる4人家族の長男として幼少期を過ごした。父は経営者でもあり、物心ついた頃には両親や部下が家屋の土間をならす傍らで現場近くの子どもたちと遊んでいた記憶がある。
ファインダーをのぞくと…
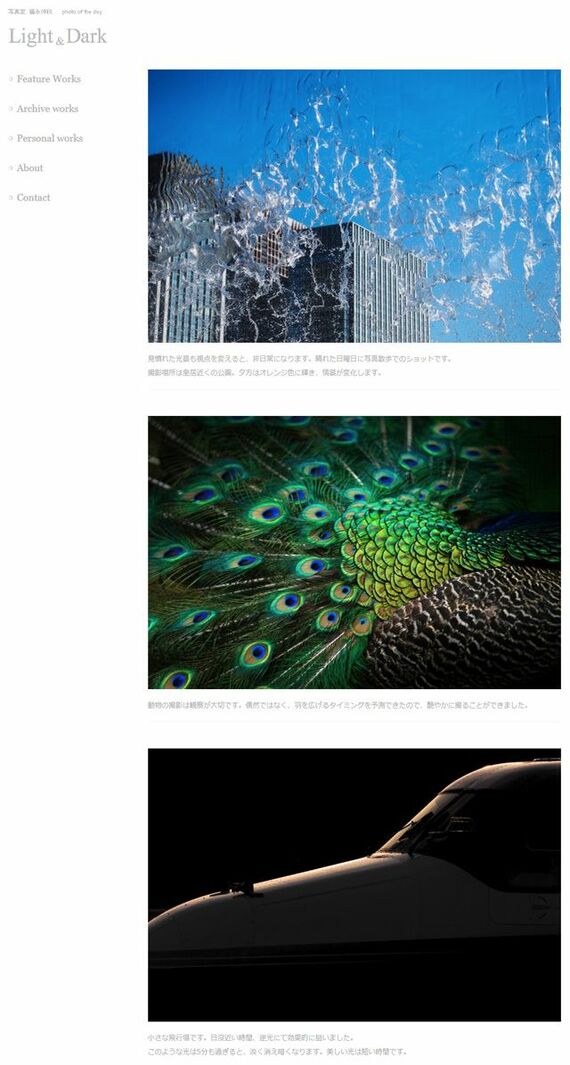
建築現場では工程の前後を写真で記録しなければならない。だから、家にカメラが転がっているのは普通のことだった。小学4年生の頃に興味を示すと、父は「これは仲秋にはまだ早いから」と言って、誕生日に110フィルム(ワンテンフィルム、ポケットフィルム)対応のシンプルなカメラを買ってくれた。ファインダーをのぞくとすぐさま衝撃が走った。
「世の中にこんな面白いものがあるんだ。何だこの面白さは、と。世界をそのままを切り取ったり、好きなように配置して切り取ったりできるのがすごいなと思いました。そのまま現在まできている感じですね」
友達にもらった鳥取砂丘の砂をコタツの上に盛って、ドクロのオモチャを乗せる。学習机から持ってきたスタンドライトでそれを照らして、ファインダー越しにベストな構図を探る。そんな遊びを終日やっていたのを覚えている。母や姉からは後に「あのときの仲秋は怖くて声がかけられなかった」と言われた。フィルムは1本24枚撮り。小遣いの関係から1カ月に1本分撮影して現像するのが限界だったため、ひたすら被写体の配置や構図、光の当たり方を考えた。考え抜いた末に月の残り日数を勘定しながら1回シャッターボタンを押す。それが楽しくてたまらなかった。
中学に入ると創作物よりも自然を切り取ることに興味を持つようになる。父の仕事を手伝ったり部活を楽しんだりしながら、暇なときには撮影しに出掛ける日々。その頃には父が一眼レフを貸してくれるようになり、シャッタースピードや絞り、ISO感度などを調整して表現方法を探る楽しさも覚えた。望遠レンズにほれ込むあまり分解して壊してしまったこともあった。

高校に入ると、ドキュメンタリー色の強い人物写真に興味を覚えるようになる。家業の手伝いとバイトで旅費を貯めて、月に1度のペースで大阪の西成に出向き、ホームレスやアウトローな人たちに声をかけてポートレートを撮った。学校では写真部に所属し、暗室の使い方もマスターした。同志と語らい、写真雑誌でさまざまな作品に触れて世界を広げていったのもこの頃だ。


































無料会員登録はこちら
ログインはこちら