中国人風刺漫画家が日本に「亡命」した事情 習近平政権下で強まる言論への規制<4>
そのヒントは王さんが最初に「お茶を飲んだ」体験を語ってくれた中にあった。問題となった作品を見せてもらった。赤や青の投票用紙を掲げる無数の手が描かれており、「一人一票で中国を変えよう」と大きな文字が記されている。中国にも選挙はある。しかし国民一人一人が投票できる直接選挙は村民委員会など末端に限られ、国の重要ポストは、国を指導する立場である共産党内の協議で決定される。
漫画はその体制を批判している。王さんがこの漫画を発表した後、ファンの一人がこれをプリントしたTシャツを作りネットで売り出した。王さんは「結構売れたみたいですよ」と笑うが、その後、Tシャツを販売した人物は逮捕されてしまい、王さんの元にも国家安全部の男が「漫画の件で来た」と現れた。
心配しているのは「組織の存在」
「私が漫画を描いた点にはあまり注目していないようで、これを描くのに他人の指示があったかどうかに関心を持っていました。彼らの怖がっているものが、話しているうちに段々と分かるようになりました。彼らは組織化が怖いらしく、単純な言論ならいいけど、デモに参加したり政治的の反対の組織的な運動をしたりすると、厳しく取り締まろうとするのです。だから彼らは私の後ろで、何らかの組織が指示を出したりしていないかを心配していたのです」
不安に駆られた王さんが、今後も漫画を描き続けていいかどうか恐る恐る尋ねたところ、「そこはあなたの言論の自由だが、描き方は抑制して欲しい」と言われたという。発信のどの部分が問題なのか明示しない点も、花夫人の場合と同様である。これは発信する側にとっては厄介である。明文化されるなどの明確な基準があるのではない。少なくとも発言する庶民の側に、その基準は知らされない。基準は当局側が恣意的に何時でも如何ようにでも変えることができるし、同時に取り締まられる側には反論の余地を与えない。
「明確に漫画を描いてはいけないと言われていたら描くのをやめたはず」と王さんは振り返るが、結局、その後も常に当局から呼び出しを受ける心の準備をしながらも、漫画を描き続け、今日に至ったという。その彼でさえ、一昨年から去年にかけ一層圧力が厳しさを増したと感じていると話す。その状況を「敏感な時期が無くなった」と表現する。これまでは全人代の開催時期や天安門事件のあった6月4日前後などは「敏感な時期」として、圧力や取り締まりが強まったが、「もはや一年中敏感だからです」と風刺漫画家らしい説明を加えてくれた。ネット上での言論統制を強める習近平政権は、何に触れられるのを一番恐れているのだろうか?
「共産党が政権を握ってから(中国で)本当の選挙は一回もありません。党内の選挙も偽物です。習近平はあらかじめ指定された後任者であり、選挙で就任したわけではありませんからね」
静かに微笑んで王さんはこう断言した。「中国共産党の統治の合法性です」。
去年12月。中国が主催するインターネットの国際会議で、習近平国家主席が演台に立った。そこで「ネットの管理方式などを各国が自主的に選択する権利を尊重すべきだ」と西側諸国などからの言論抑圧への批判をけん制し、ネット上での言論の自由について考えを明らかにした。
「ネット民の交流の思想と意見表明の権利を尊重するからには、法に基づき良好な秩序を築かなくてはいけない。ネット空間は無法地帯ではない。ネット空間は虚構であるが、ネットを運用する主体は現実である。皆、法律を遵守しなくてはならない」
かつて毛沢東が巻き返しを図るため、開放的な思想や知識人を弾圧した血塗られた歴史、文化大革命を引き合いに、今「ネット上の文革」が起きているなどとも揶揄されている。相次ぐ言論抑圧は、国民を統治し続ける能力に対する共産党自身の自信の無さの表れなのか。そこまでして中国が守ろうとしているものは、国民が自由に考えを述べられる空間と引き換えるに本当に値するものなのだろうか。
記事をマイページに保存
できます。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら
印刷ページの表示はログインが必要です。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら







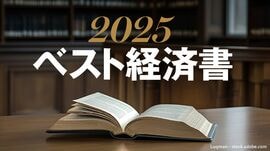
























無料会員登録はこちら
ログインはこちら