マイナス金利の究極の効果は「財政救済」だ 市場を歪める政策をどこまで続けるのか

城が内側から自壊したかのような政策導入
日本銀行は2016年1月29日の金融政策決定会合で、マイナス金利の導入を決定した。といっても超過準備預金のすべてにマイナス金利を付するわけではない。これまでプラス0.1%の金利を付けてきた超過準備預金の2015年平均残存額と比べた増加分に対して、マイナス0.1%を課するという方式だ。
それでも「マイナス金利」という衝撃的なヘッドラインの威力は凄まじく、市場はマイナス金利が全面的に適用されたかのように反応した。すでに0.2%しかなかった10年国債金利が、さらに0.1%まで低下した。
実は、マイナス金利はこれまでにも円金利市場で発生していたが、それは金融機関同士の取引で生じる「実質的」なもので、一般投資家からは見えにくかった。日本人が海外ビジネスに必要なドル資金を調達するために「円をマイナス金利で貸す」という必殺技を繰り出したことが、円金利をマイナス化させたのである。

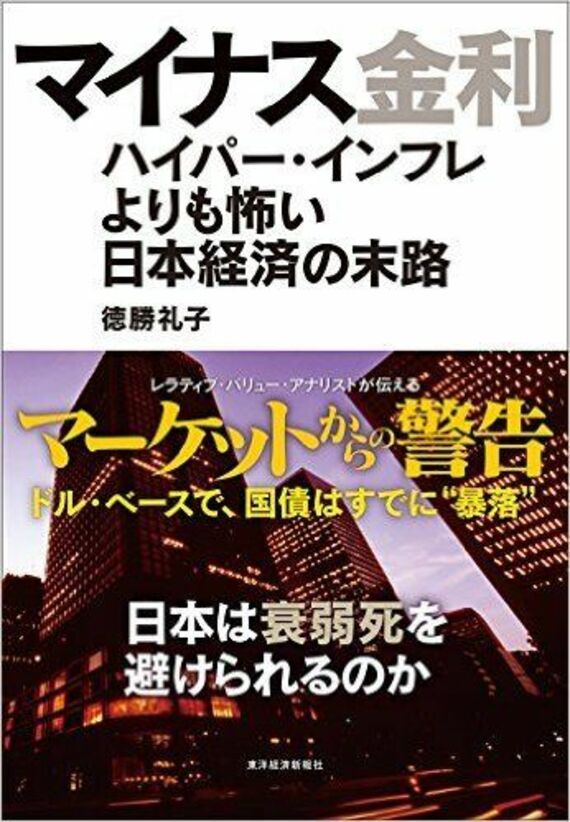
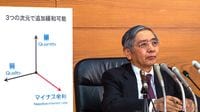






























無料会員登録はこちら
ログインはこちら