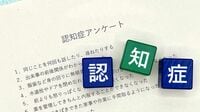俳優・山本學が感じた【認知症で衰えるのは「知の働き」だけではない】という"当たり前の現実"
ところが最近、誰とでも対等で、人のためになれればいいと思って生きてきたのに、頑固で怒りっぽくなっていることに自分でも驚いてしまったんです。これは、脳の前頭葉の問題、つまり認知症と関係があるのかと思っていたんですよ。
朝田 そこはおっしゃるとおりで、前頭葉は意思決定を司っており、まさに人間性を形づくる部分になります。
記憶や物覚えのことばかり言うけれど、認知症で最初に障害が起きるのは、どうも意思のほうだと、最近になって考えられるようになってきたんですね。前頭葉が萎縮して神経細胞が失われることで、人間性や行動、語彙力に衰えや問題が出てくる、というわけです。
しかしね、學さんのお歳からすれば、極めてお元気なほうだと思いますよ。そこでお聞きしたいのですが、「良い老い方」とはどのようなものだと思われますか?
いくつになっても、自分が「老いている」とは思えない
山本 頑固じゃなくなること。自分の受け取り方や意見を押し通さないことです。人が言ったことに対して、「自分はこう思う」とすぐに反応するのではなく、本当にその人が言いたいことは何か、言っていることの裏に意図がないかと考えながら、まずは話を聞く。
こういうのは、やはり歳をとるとできなくなってきますね。話を聞かずに結論づけてしまうとか、相手の考えや意図には無関心なままで聞いている。
そういう相手を慮る気持ちが歳をとるとなくなっちゃって、誤解したままで自分の話を続けようとするから、頑固に見えてしまうんでしょうね。
朝田 昔から「老人の知恵」と言い習わしたように、積み重ねた知見や経験で意見の衝突を丸く収めるのが長老の役目とされてきました。でも、最近はどうも違ってきているように見受けられますね。
山本 ところで先生、一言いいですか? 先生は今、「學さんのお歳からすれば、極めてお元気なほうだと思いますよ」とおっしゃいましたが、年寄りはいくつになっても、自分が「老いている」とは思えないのです。