そこには、女性たちが成長過程で声を封じられてきた問題も背景にありそうだ。「お母さんが自治会に出たら『女が意見を言うな』と言われた。進学校なのに『女の子が勉強をがんばらなくていいんじゃない?』と進路指導の先生に言われた。『弟に教育投資したいから、高校を卒業したら家にお金を入れてね』と母親に言われた。
こうした露骨な例は少なく、実際はもっとやんわり、『女性は気が利く人間になりなさい』と言われることが多いです」と山本代表。自己主張せずサポート役に回るよう誘導される積み重ねが、女性たちを黙らせてきたのではないだろうか。
地方女子プロジェクトが行ったインタビューでは、心のモヤモヤを初めて口に出した女性や、違和感・不満を持つ自分をおかしいと思い込んでいた女性が何人もいたそうだ。地元の人に自分だとバレないよう、映像で声を変える、顔を隠すなどの配慮を求める女性も多い。
声を上げたからこそ見えてきた希望も
一方で、プロジェクトで声を上げ変わってきたこと、見えてきた希望もある。
「絶対地元へなんか帰らない」と言っていた女性がプロジェクトにかかわるうち、「自分が変えないと」と地元県庁への就職を決めた。地方議員に立候補するつもりの女性も何人もいたのだ。
1989年の人口動態統計で合計特殊出生率が過去最低の1.57に低下した、いわゆる「1.57ショック」から36年。
経済的自立を求める女性が増えたのに、地域や経済を担う仕組みが変わらないのでは、ギャップが大きくなるばかりだ。少子化が一向に改善しないのは当然だろう。2024年の合計特殊出生率は1.15まで低下している。
保育園の拡充や出産祝い金など目先の支援だけで、現状は変えられない。地方女性たちの不安は、自分を生かせる場がないこと、家族の経済力を当てにするリスクの大きさに気づいていることから来る。
まず、女性が男性と同じように、経済的に自立できる場が必要だ。女性が自活すれば、人生の選択肢が増える。パートナーの男性がいる場合、彼の重荷も減らせる。
万一のときに自分が家族を守れる力も得られる。性別を気にする前に1人の人間として認められ、生きていける環境があること。結婚する・しない、子どもを持つ・持たないは、その後に本人が決めることだ。
大人たちは少子化の責任を若い女性に押しつける前に、自分たちがここ数十年棚に上げてきた問題が何だったのか、彼女たちの声に耳を傾け、改めて考え直す必要があるだろう。

記事をマイページに保存
できます。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら
印刷ページの表示はログインが必要です。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら

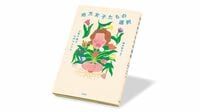





























無料会員登録はこちら
ログインはこちら