家族単位の付き合いが多い地方では、「子どもがいないと、地域とつながるツテがない」問題もある。
「自治体の子育て支援も、家族に頼れることを前提としたケースが多いです。産後ケアや一時的なシッターを探しても見つからず、親御さんとケンカしたら、子どもを預ける選択肢がなくなる人もいました」と話す山本代表。
「親戚が集まると、自分だけがシングルという状態がつらいから、30歳になって東京に出てきた、という人もいます。特に印象的だったのは『女性で独身だと透明人間のよう』と言う方でした」
地元の山梨県で暮らす山本代表自身も、昔からの友人は地元を出たか子育て中で、話が合う人がおらず疎外感を抱きがちだ。

「産めハラ」をなくすために必要なこと
山本代表は、性別役割分担意識が濃厚な職場環境を変えることが、「産めハラ」をなくすために必要と考えている。職場や就活先の企業から、子育てのために退職する前提で扱われる女性は多い。
「東京の大企業やベンチャー企業では、育児との両立支援をする、男性の育休取得率が上がるなどしていますが、地方の中小企業では、アップデートどころか前提が違い過ぎます。男性の長時間労働が是正されれば、男性が家庭に入り込める時間が増え、女性がケア役割を担う前提も消え、やがて女性の多様性も認められていくのではないでしょうか」(山本代表)
地方女子プロジェクトは、政治・行政へもアプローチしている。自治体に伝えるのは、女性も仕事をしたいが、地元に働く場がないこと。結婚・出産に関する周囲の圧力が強いこと。
さらに、「地域のお祭りなど交流の場で、女性は裏方の役割ばかりなのは嫌だ」、といった声もある。このことを伝えると、「確かにそういう傾向はあるけれど、女性が出ていく理由になるとは思っていなかった」と返されたそうだ。
今年3月には、「若者や女性に選ばれる地方をつくる」を主要政策の1つに掲げる石破総理大臣(当時)が地方出身者との意見交換会を開き、山本代表も招かれた。

地方女性が置かれている現状を訴えたところ、横で聞いていた赤沢経済再生担当大臣からは「女性が1人でも生きていける地方というのは新しい切り口として学びになった」と言われた。女性たちの苦しみは、政府や行政にまったく伝わっていないのだ。

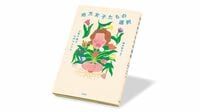





























無料会員登録はこちら
ログインはこちら