「経済格差」が「栄養格差」を招き、「栄養格差」が「健康格差」を招く悪循環を作り出すのだ。
物価高が長期化すれば、子どもの場合は成長、高齢者の場合は、持病やフレイルの悪化などで最悪寿命が短くなるだろう。「栄養の切れ目」が「命の切れ目」になるのだ。社会疫学研究者のイチロー・カワチは、近年日本で栄養状態などによる「命の格差」が急激に広がり、「長寿国家」が瓦解すると警告している(NHKスペシャル取材班『健康格差 あなたの寿命は社会が決める』講談社現代新書)。
すでにアメリカとイギリスでは、過酷な「栄養格差社会」が到来している。
「健康的な食品は、健康的ではない食品に比べてカロリー当たりの値段が2倍以上高く、入手も困難である」「国民のうち最も恵まれない人々の5分の1は、政府が推奨する健康的な食事を摂るためには可処分所得の45%を食費に費やす必要があり、子どもがいる世帯ではその割合は70%に上昇する」といった実態があり、低所得者層ほど病気になりやすく短命になりやすいという傾向が加速している(『The Broken Plate 2025』/2025年1月29日/The Food Foundation)。
奪われるのは命だけではない。究極的には表面上のスティグマ(烙印)などよりも、自分の稼ぎだけではわが子を満足に食べさせられないという負い目こそが自尊心を深く傷付けるのだ。経済学者のリチャード・ウィルキンソンらは、所得格差の大きな社会ほど、うつ病、不安症の発症率が高いことをデータで示した(リチャード・ウィルキンソン/ケイト・ピケット『格差は心を壊す 比較という呪縛』川島睦保訳、東洋経済新報社)。
また、そのような社会では実力主義が蔓延し、社会的地位などに対する依存が強く、市民の社会活動への参加率が低い傾向が明らかになっている。要するに、収入が低いのは本人の努力が足りないからという「自己責任論」が横行しやすいのである。ウィルキンソンらは、「不平等が心の病に影響を及ぼす経路は、自分の苦しみを他人に知られたくない気持ちや、その責任は自分にあるのだとする思い込みと深く結びついている」という(同上)。
「栄養の格差化」から目を背けてはいけない
先の総裁選における物価高対策では、所得税減税、地方交付金、給付付き税額控除などが挙がったが、候補者たちからはあまり危機感が感じられなかった。
「栄養の格差化」は取り返しのつかない禍根を残すことになるは明白だが、おそらく大半の人々も高齢者や中高年者が持病の悪化などで亡くなったり、あるいは子どもの学習意欲が低下したり、感情的に不安定になっても「物価高」のせいにしないだろうからだ。「自己管理ができていないのが悪い」というフレーズで一蹴するかもしれない。
構造的な要因がもたらす格差によって人々の心身が破壊されるプロセスは漸進的なもので、目にも見えなければ、音として聞き取ることもできない。だが、その影響は国民全体のパフォーマンスに関わるほど甚大である。あたかも希釈された毒が少しずつ体内に蓄積し、致命的な結果をもたらすように、わたしたちの社会を内側から溶かしてしまうだろう。
記事をマイページに保存
できます。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら
印刷ページの表示はログインが必要です。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら

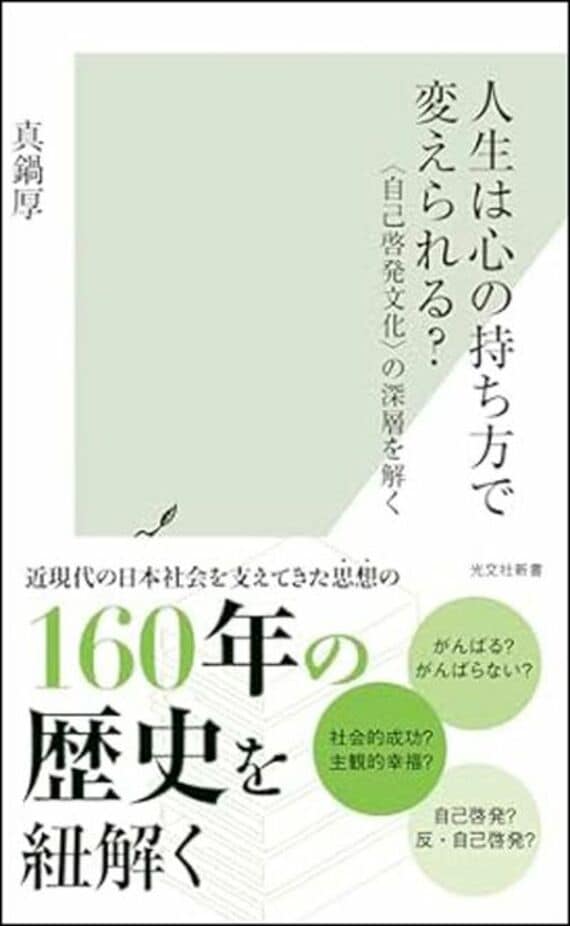






























無料会員登録はこちら
ログインはこちら