他人から好かれる「人間性」を身につけるには? 誰でもできる"極めて重要な行動"を哲学研究者が伝授
一人称的経験をシェアし合うことによって、より豊かな人間性を獲得することにつながります。先ほど、経験と思考活動こそが人間性を形作ると述べました。若い人の発言がしばしば大言壮語であったり、振る舞いの点で失敗してしまったりすることが多いのは、さまざまな観点において経験がまだ少ないからです。
経験を積み、「自分は何がしたいのか」、「何をすべきなのか」、「〈したいこと〉と〈すべきこと〉の間で何ができるのか」ということに思案をめぐらせていく中で、少しずつ人間性が形成されていきます。
このとき、経験が少なければ、自分が成長する機会も、自分自身の在り方について考える機会も与えられないでしょう。逆に言えば、一人称的経験をシェアし合うことによって、自分自身の人間性を広げることにつながります。「もし自分がそのような状況になったら、どうするだろうか?」ということを追体験の中で考えることが、人間性を養う機会になるのです。
また、一人称的経験をシェアすることは、対話者同士が相互理解を獲得することにもつながります。「この人はこのような経験をしたのだ」、「だから、今のような考え方をするに至ったのだ」というふうに相手を知ることは、相手という存在を形作ってきた当のものを理解することにつながります。
人間性は環境や経験によって変化しうる
私たちの考え方の違いは、多くの場合私たちの経験の違いに起因します。人それぞれ、考え方や感じ方が異なっている(まさに「十人十色である」)のは当然のことです。それらの違いを尊重するのも大前提です。ここで大切なことは、そうした違いがあることを理解するだけでなく、いったいいかなる経験の違いが人間性の差異をもたらすのかをお互いに吟味し合うことなのです。
生まれつき、人間の本性が決まっているわけではありません。その人がそこに巻き込まれている環境や経験が、その人の人間性の多くの部分に影響を与えるのです。
このことは、逆に言えば、新しい環境に身を置いたり、別様の経験をしたりすることによって、その人の人間性はいくらでも変化しうることを意味します。こうした変化の可能性を確保するアクティビティこそ、対話なのです。
記事をマイページに保存
できます。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら
印刷ページの表示はログインが必要です。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら

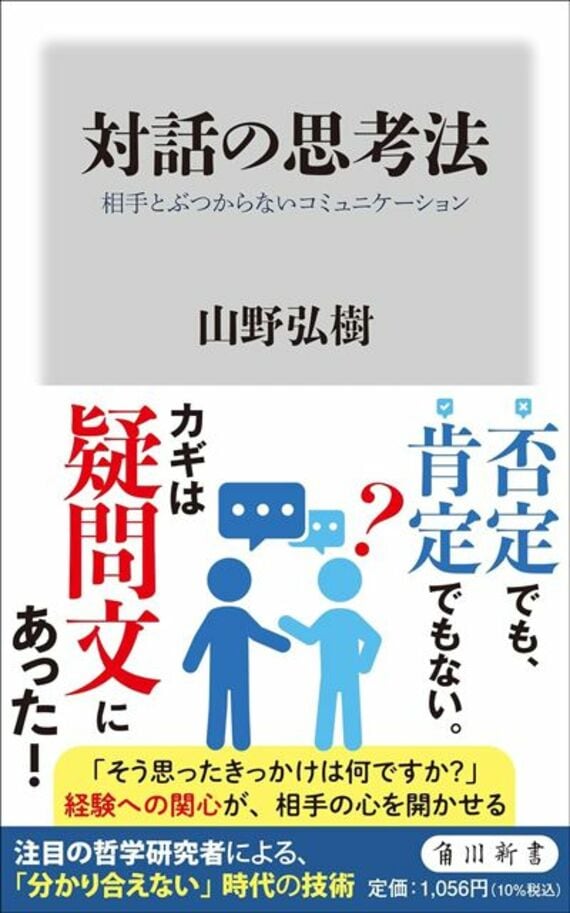






























無料会員登録はこちら
ログインはこちら