パンもパスタも“小腸”の大敵に? グルテンが引き起こす、体の「サビつき」と「炎症」の真実
小腸の粘膜上皮は絨毯の毛のようになっており、表面積がとても大きくなっています。ところがひとたび腸に炎症が起きると、細かい毛のような部分が扁平になってしまいます。扁平になれば当然、表面積が減ってしまうのは想像できるでしょう。そうなれば、栄養を吸収すべき面積も減ることになり、栄養障害につながります。
体内の細胞がサビる原因
②疲労感や老化を招く
老化を引き起こす原因に活性酸素があります。活性酸素がなんとなく体に悪いものだということは、知っている人も多いでしょう。
活性酸素はひと言でいえば体の中に起こるサビのこと。酸素は人間にとって必要なものですが、ひとたび活性酸素に変わったとたん、体内の細胞を酸化(サビ)させ、細胞の正常な機能を失わせてしまいます。その結果、老化やさまざまな病気を引き起こすのです。シミやシワはもちろん、動脈硬化や糖尿病、がんの引き金になることさえあります。
私たちは生きているだけで活性酸素を発生させています。ストレスや喫煙、過度なアルコールや激しい運動、紫外線、食品添加物の摂取などは、活性酸素を発生させる原因となります。さらにグルテンは持続的に腸の粘膜で炎症を起こし、活性酸素を体内に送り込み続ける原因になります。
一方、体内では活性酸素を除去してくれる物質も同時に働いています。その1つがグルタチオンというペプチドです。グルタチオンの材料の1つに、システインというアミノ酸があります。実はグルテンの代謝産物は、システインの取り込みを阻害することがわかっています。
つまり、小麦のグルテンで活性酸素が大量につくられたうえ、その活性酸素の除去が阻害されてしまうのです。その結果、非常に疲れやすくなったり、老化が進みやすくなったりしてしまうというわけです。
グルテンの影響を受ける人の小腸の粘膜は、荒れているとお話ししました。粘膜の荒れ=炎症なのですが、グルタチオンが欠乏すると、この炎症もなかなか治まることがありません。小麦や乳製品を食べ続けていると、一向に腸内環境が改善しないのは、このような背景があるからなのです。
記事をマイページに保存
できます。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら
印刷ページの表示はログインが必要です。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら

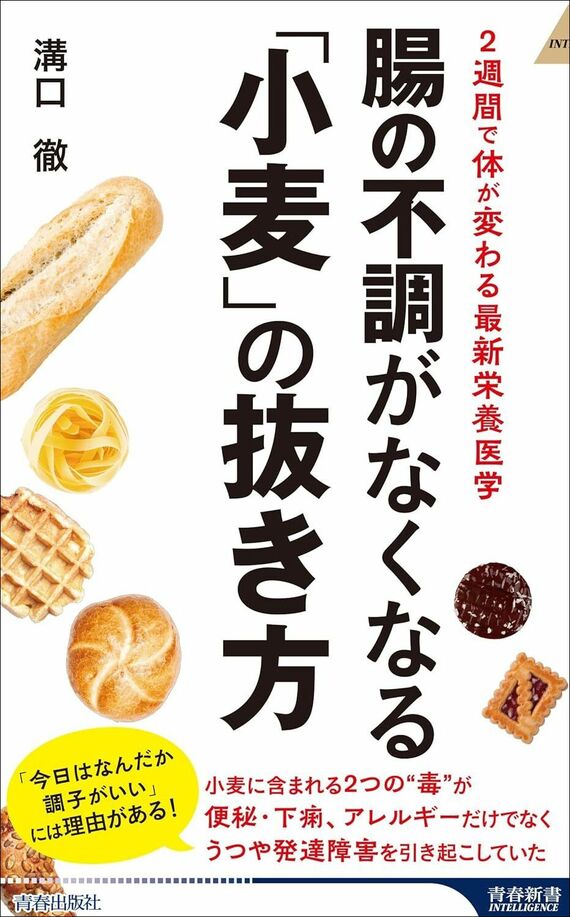






























無料会員登録はこちら
ログインはこちら