GIGAスクール構想第2期で補助金増額。Windowsタブレット減少でiPadとChromebookが二分。デバイス価格高騰で地方自治体の負担増が課題に
まず、ネットワークの問題。補助金が出たのはデバイスに対してなので、Wi-Fiなど通信ネットワークの確保は地方自治体に委ねられていた。実は、学校の通信にかかる負荷というのは想定以上に大きい。たとえば、オフィスであればそれぞれの仕事に応じて通信が発生するが、学校の場合、先生が「このアプリをダウンロードして下さい」と言った途端に35人の児童・生徒がアプリのダウンロードを行う。しかも、ひとりでもダウンロードできないと、授業が止まることになりかねない。学校のWi-Fi設置には、それなりの知見を持った業者の選定が必須で、そこがネックになった学校も少なくない。
各地方自治体に委ねられた機種選択も課題だった。MM総研の調査によるとChromebookが約42%、WindowsタブレットとiPadがそれぞれ約29%になっていたが、このうちWindowsタブレットの評判が悪く、バッテリーライフの短さや、OSのアップデートに時間がかかること、故障が多いことなどが問題になっていた。これはWindowsタブレットに課題があるというよりは、4万5000円という政府補助金の枠内で買えるWindowsタブレットにスペックの制約が大きかったというべきだろう。安価なデバイスを買って、使い物にならなかったという例は少なくなかった。
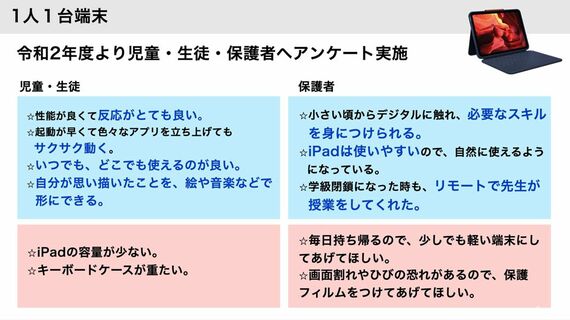
iPadの場合、ほぼ一番廉価な標準モデルのiPad一択になるが、ChromebookやWindowsタブレットの場合は、どんなハードを導入するかによって費用は異なる。そして、予算を限ると、性能的に制約が出てくるというわけだ。
また、実際問題として、端末本体だけでなく、クラウドサービスの費用や、MDM(端末やアカウントを管理する仕組み)、セキュリティリスクへの対策などにも費用がかかる。地方自治体に予算があるか、また教育に投資する覚悟があるかによって、多少の格差が生まれてしまっているのも現実だ。































無料会員登録はこちら
ログインはこちら