おばけを見ることができる場所とは、実は実祖母の家のこと。だが、始まりが「僕のおばあちゃんの家の話なのですが~~」だと、たっくーさんのことを知らない人にとって、その祖母はさらに遠い存在となり、興味を持ちづらいというのだ。
(※この祖母の家で起きた、身の毛もよだつ話はこちらからマンガで読めます)
また、状況説明を細かくし過ぎると、視聴者が興ざめしてしまう。そのため、説明は最小限に抑え、後は会話劇で物語を進めていくのがポイントだ。Aさんの友だちのBさんが体験した話、などという設定の怪談も、内容がいくら怖くても、説明が複雑になるためできるだけ避けているという。

「ギシギシと」「そーっと」の重要性
怪談師たちによるイベント『稲川淳二の怪談グランプリ リターンズ 2024』で、たっくーさんは見事優勝したが、そのときも前述のように、シンプルな説明と会話劇が中心の怪談を披露した。この話法は落語に近いかもしれない、とたっくーさんは話す。
「そのときの状況が一番頭に入ってきて、実際の会話を聞いているような臨場感が生まれるのは、会話劇だと思うんです。登場人物の口調や言い方を真似るだけでも、怖さはぐんと増すと思います。僕はYouTuberになる前は芸人だったのですが、その頃にモノマネを持ちネタにしていたことも怪談に生きているかもしれないですね」

あらすじや結末そのものだけでなく、怖い話ならではの表現も重要だという。たとえば、「ギシギシと」「そーっと」などの表現や、具体的な地名、歴史を感じられる伝承など。それらが風情やリアリティ、不気味さなどにつながり、怖さを生み出していくのだ。
もうすぐ夏本番。怖い話のイベントや番組が盛んになるこの季節を、ファンは心待ちにしているだろう。世代や性別を問わず盛り上がれるのが、怖い話のいいところ。今年は語り手に回ってみるのも面白いかもしれない。
前編では、【「母はパチプロで貧しい家庭でした」「月給9万円で名刺1000枚を配り…」“怖い話”で280万人超から支持される人気YouTuberの《数奇な半生》】をたっくーさんが語っています。
記事をマイページに保存
できます。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら
印刷ページの表示はログインが必要です。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら













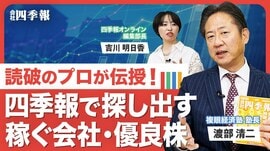
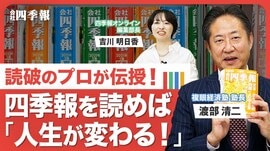






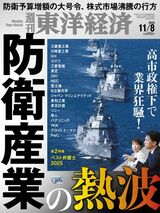









無料会員登録はこちら
ログインはこちら