その後、怪談や実際に起きた事件などの配信もするようになり、チャンネルはますます人気に。配信内容のヒントを得たのは、人気番組『奇跡体験!アンビリバボー』だった。超常現象や怪奇現象など、広い意味での「怖い話」を紹介し、飽きさせることなく視聴者の知的好奇心を刺激している点を参考にしたという。
インターネットの普及に伴い、注目を集めるようになったジャンルが「陰謀論」だと、たっくーさんは続ける。ネット上には膨大な情報が飛び交い、新型コロナや災害、戦争など有事の際には、真偽不明なそれで溢れかえる。
最近では兵庫県知事をめぐる問題やコメ不足のときもそうだ。黒幕がいて、ある目的のためにわざとこのような事態を引き起こしている、など、まさに「信じるか信じないかはあなた次第」だが、物事の裏に隠された真相があると言われたら、聞きたくなってしまうのが人間の性だろう。
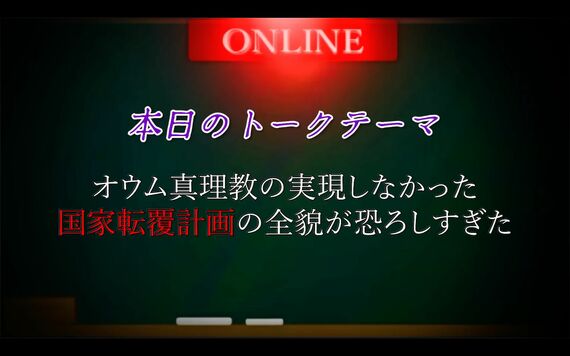
「オカルト」を信じる人が増えた
このような状況で、オカルトがオカルトではなくなってきている、とたっくーさんは考察する。
「都市伝説や陰謀論などのオカルトは、これまではファンタジーとして捉えていた人が多かったと思います。けれど、ネットで情報が身近になり、たくさんのオカルト話を聞くうちに、『本当にそうなのかもしれない』と感じる人が増えたのかなと。だからこそ、もっと世の中の真実を知りたいと思って、YouTubeなどでオカルトを見る人も多くなったのではないでしょうか」
そんな風潮だからこそ、たっくーさんがオカルト話を配信する際、心掛けている点があるという。それは、多角的な視点で紹介すること。
「この事件の黒幕はあいつだ!」と、1つの結末に視聴者を誘導するのではなく、「こう言っている人がいる」「ああ言っている人もいる」「その根拠はこうだ」とさまざまな判断材料を提示し、結論は視聴者にゆだねる。
そうすることで、いたずらに視聴者を印象操作することを防ぐと同時に、多様な考え方の人々が共存できて、ここまで規模の大きなチャンネルになったのだ。













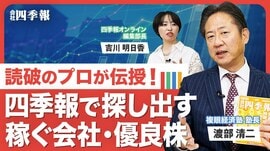
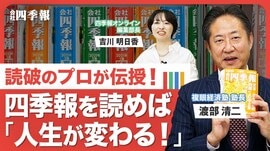






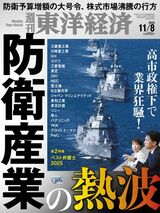









無料会員登録はこちら
ログインはこちら