では、消費税はなぜ逆進的といわれるのか。そこには、見せかけのカラクリがある。
先の表の負担額を、課税前収入に対する比率に直したのが、下表である。

消費税の負担率をみると、第Ⅰ階級が最も高く、第Ⅴ階級が最も低い。つまり、低所得者ほど負担率が高いという意味で、「逆進的」ということになる。ただ、負担率の差は、2%ポイント程度にとどまる。
なぜ、こうした現象が観察されるのか。
それは、貯蓄率に差があるからである。通常、高所得者ほど、今年稼いだ所得のうち貯蓄に回す余裕があって、貯蓄率が高い。
貯蓄率が高いことと、一見すると消費税負担率が逆進的にみえることとは密接に関係がある。なぜならば、負担率の分母の所得は、消費する分もあれば貯蓄する分もある。他方、分子の消費税負担額は、消費しないと実現しない。今年貯蓄した分は、消費税はかからない。だから、高所得者ほど比率に直すと消費税負担率が低くなる。
だからといって、高所得者は消費税負担を回避し続けられるわけではない。貯蓄は将来消費するために蓄えられているものだから、今は消費税を払わなくても、将来貯蓄を取り崩して消費する際には消費税を払う。
そこまで見通して、消費税負担を語らなければならない。経済学的には、消費税は逆進的な税ではなく、生涯所得に対して比例的な税である。
本当に「負担減」を実現するには
第Ⅰ階級にとって、消費税負担率は約4.6%で重い、と目くじらを立てるなら、むしろ社会保険料負担率を取り沙汰したほうがよいだろう。第Ⅰ階級の社会保険料負担率は12.6%と、消費税負担率より断然高いのである。
低所得者の社会保険料負担率は、今までにも講じられてはいるが、まだまだ不十分だろう。消費税を廃止しても、負担率を5%も下げられない。軽減税率だけを引き下げたところで、負担率はもっと下がらない。社会保険料負担をいかに下げるかを真剣に考えることが、低所得者対策にもなる。
低所得者向けの給付は、確かにその助けにはなろう。しかし、臨時的な給付は付け焼き刃である。社会保障の一環として、生活保護水準よりは高いが低所得で生活に困窮する国民には、生活保護制度とは別に、恒久的な制度として措置する必要がある。
それを裏付けるには恒久的な安定財源が不可欠である。その財源確保をどうするか。参議院選挙中に議論が深まらないなら、参議院選挙後に宿題として残される課題である。
記事をマイページに保存
できます。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら
印刷ページの表示はログインが必要です。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら




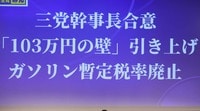



























無料会員登録はこちら
ログインはこちら