「ポケモン生態図鑑」が爆売れ 行動生態学の専門家が解説したポケモンの“生き物らしさ”とは?
この書籍では、ゲーム内の「ポケモンずかん」による説明文を基に、ポケモンたちがどのような生態を持っているのか、イラスト付きで解説するといったものになっている。

やはりポケモンは不思議な生き物なので道理に合わないことも多く、そのタブーには触れないようにしつつも生き物としてのポケモンを捉えているのが特徴だ。ポケモンずかんに忠実なのも重要で、著者の推測があるにしても「~~かもしれない」といった描写にとどまっている。
アイスクリームのような姿をしたポケモン「バニプッチ」が南国で冷房代わりに愛用されているだとか、大切にされすぎた結果増えすぎた「ラプラス」の様子が描かれるなど、ゲームでは見られないポケモンの生き物らしさが存分に描かれており、ポケモンファンが喜ぶのも納得の出来栄えだ。
総ルビになっているうえ、イラストの点数も非常に多い。確かに子供向けの本なのは間違いないのだが、実はこういった「ポケモンを生き物として捉える」というのは、このIPにかなり欠けているものであった。
そもそもポケモンが持っている大きな矛盾
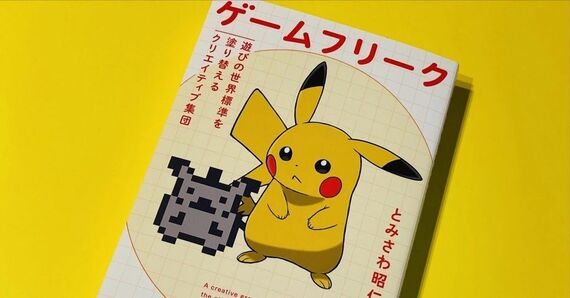
そもそもゲーム『ポケットモンスター』のアイデアは、昆虫採集とカプセル怪獣からきている。
ポケモンを捕まえてバトルで戦わせたり、あるいは全種類を集めるというのは、まさしく昆虫採集である。また、ポケモンは凶暴であったとしてもモンスターボールに収納できる。これは『ウルトラセブン』などに登場する「カプセル怪獣」から大きな影響を受けているのは間違いないだろう。
昆虫ならばそれなりの生態があって当然だが、怪獣になると話はややこしくなる。フィクションの存在なので、どうやって生きているかあまり考えられていないのだ。
しかも、ポケモンは「ピカチュウ」をはじめとする哺乳類のような存在も多数おり、彼らは人間のパートナーと捉えられている。人間と密接につながりを持っており、もはや単なる野生生物というわけでもない。
つまりポケモンは捕まえてもよい昆虫でもあり、フィクションらしい怪獣でもあり、ペットのような存在でもあるわけだ。ゲームをおもしろくするためには致し方ないが、これは極めて矛盾した存在といえる。

この矛盾があるため、ポケモンの生態が詳しく描かれることはない。たとえばガス状ポケモンの「ゴース」は一瞬吸い込んだだけで気絶するほどの毒を持ち、その毒性はインドゾウも2秒で倒れるほどだ。資格なしのポケモントレーナーが扱うにはあまりにも危険すぎるが、実際に何かを殺す様子が描かれることはない。


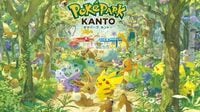




























無料会員登録はこちら
ログインはこちら