宮下:小学校から高校までの指導要領の改訂でも、学生たちの「考える力」を伸ばそうという方向に進んでいるので、やはり「答えがない問題」に立ち向かうための力が必要だということは認識されてきていると思います。それを私なりの言い方で、若い人たちに伝えたいと思って本を書きました。
私は小さい頃から「なんでだろう」と考え続ける子どもだったのですが、よくやっていたのが、目を閉じて右目の右端を指でそっと押してみること。すると、なぜか左目のほうに光を感じられる。左右が逆に反応しているのが面白くて、ずっと試していたのを覚えています。
窪田:目の端を押すことで、視覚の受容体が刺激されて光が見えているのですね。
「なんで?」の疑問から研究への扉が開かれる
宮下:はい。もともと画像工学科の出身でカメラの構造についても学んだのですが、左右が逆になるのはカメラの仕組みと一緒ですよね。実は、これは授業のデモンストレーションでもよく使っているのですが、それは研究の面白さを感じてほしいと思っているからなんです。
つまり、この世に光がなくても光として感じることはできる。それと同じように、たとえば味覚の分野だったら、「電気刺激を使うことで、塩を足さなくても味を変えられる」という発想ができるかもしれない。学生たちが研究に興味を持つきっかけになればと思って、いつも使っているたとえ話なんです。もちろん目を押すときは強く力を入れずに、そっと優しく、と言っています(笑)。
窪田:目のメカニズムはとても面白いので、それを知ってもらえるのは嬉しいです。些細なことでも「なんで?」と疑問を感じるところから、研究への好奇心が湧いてきますからね。
次回は、日本とアメリカの教育を比較しながら、これからの人材に必要な「問いの立て方」について話し合います。
(構成:ライター安藤梢)
記事をマイページに保存
できます。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら
印刷ページの表示はログインが必要です。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら

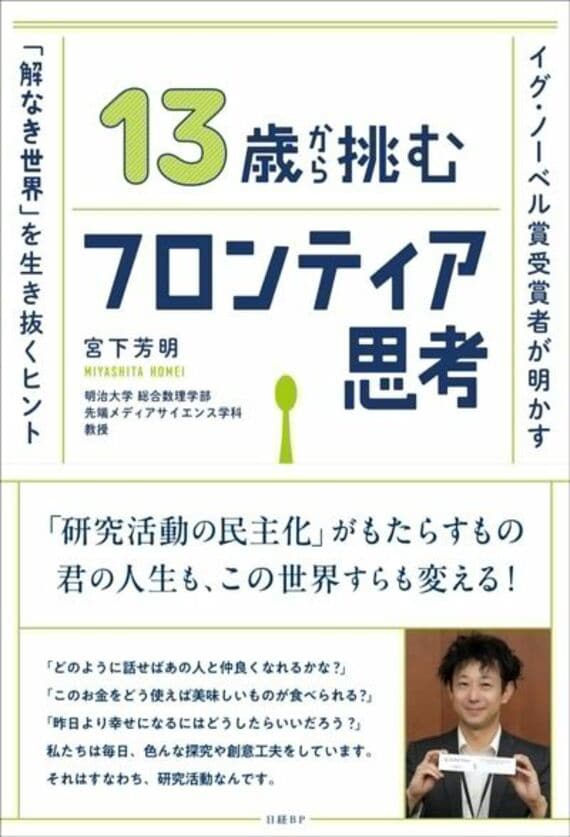






























無料会員登録はこちら
ログインはこちら