澪が海外で大人気「宝酒造」驚きの日本酒革命 アメリカの酒蔵で「イノベーティブなSAKE」を開発

海外でウケる日本酒をつくる
宝では、「海外でウケる」日本酒を製造・販売しているという。「海外でウケる」日本酒とはいったいどんなものだろうか? 森三典社長によると、日本人の感覚では「料理に合わせるのは難しい」と判断されてしまうような酒だそうだ。理由を知るため、少し歴史をたどろう。
宝が1951年に日本酒を海外で販売しはじめた当初は、いわゆる「和食」に合う酒を提案していたという。だし、米、発酵調味料を柱に、野菜、魚も味わうヘルシーな料理に合う酒だ。
だが前編でも解説した通り、酒は食と違って嗜好品であり、現地のライフスタイルや食文化と一緒に育まれていくもの。「和食」に合う酒は、欧米ではすぐには受け入れられなかった。
なぜならアメリカでは、寿司のような日本食に加え、とんかつソースやわさび、唐揚げにたこ焼きなど、濃く刺激のある味のものが人気となったからだ。宝が「日本食」と位置づける、現代の日本で親しまれるメニューが注目を集めたのだ。

そこで同社は伝統的な製法による日本酒だけではなく、現地の「日本食」の濃い味に負けない、パンチのある甘さ、濃さの日本酒も必要と判断。香りの強い吟醸酒や濃厚なにごり酒などを販売してみると、これが当たった。欧米では食中酒として歓迎されたのだ。
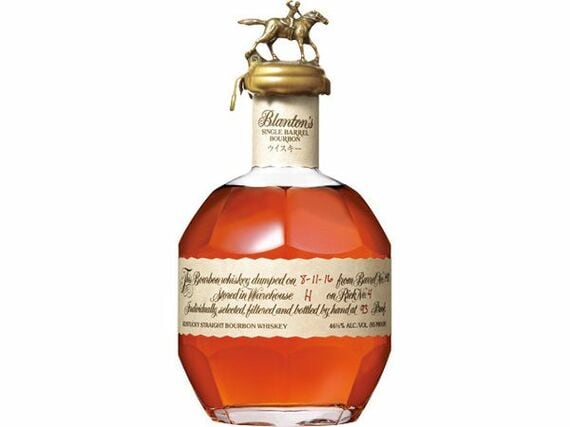
昨今はそれにプラスして、濃い味を邪魔しないすっきりした日本酒や、チューハイなども提案している。また、あまり知られていないが同社は、1986年から海外でウィスキーも販売している。
2024年3月期の連結決算では、バーボン・ウィスキー「ブラントン」ブランドが全米中心によく売れ、約75億円の売り上げを上げている。
エリアに合わせた、イノベーティブな「SAKE」も開発
そんな宝が今注力しているのが、日本の伝統製法をベースに、現地の嗜好・ニーズに合わせた「イノベーティブ(革新的)なSAKE」の開発だ。米や米麹を使いつつも、さまざまな素材を融合したり、酵母を変化させてチャレンジしているという。
2022年からは世界を4つのブロックに分け、現地にいる食材卸の担当者と、酒造のメンバーでチームを編成。各ブロックのニーズをきめ細やかに調査し、それぞれに対応した商品を、日本、そしてアメリカ等で販売している。
2024年には、「MU|WA(ムワ)」「Sho Chiku Bai OCEAN VIEW」「Sho Chiku Bai SKYLINE」と3種の「イノベーティブSAKE」が誕生した。カリフォルニア州バークレーに酒蔵を持つTakara Sake USA Inc. (以下、米国宝酒造)が開発したものだ。

「MU|WA(ムワ)」はバーボンの樽で寝かせる純米酒で、熟成感があって味が濃い。対して、「Sho Chiku Bai OCEAN VIEW」「Sho Chiku Bai SKYLINE」はどちらも酸味が強い純米酒だ。「Sho Chiku Bai OCEAN VIEW」はオイスターバーやシーフードの店を想定して作られており、魚介類によく合う。
一方、「Sho Chiku Bai SKYLINE」は、肉料理に合うよう作られている。いずれも現地の飲食店で試飲してもらい、意見をもらいながら味を調整したそうで、これまで日本にはなかった味わいだという。
開発には、丸2年の歳月が費やされた。ワインではブドウの生育地の地理、地勢、気候で味が異なる「テロワール」という言葉をよく耳にするが、日本酒も同様だからだ。水も米も気候も熟成環境も異なるアメリカでは、「日本で蓄積したノウハウ上はできる」ことも、「やってみなければわからない」の連続だった。
「ですが弊社には、1983年からアメリカで酒造りをしているメンバーがおり、長年のノウハウが蓄積されています。だからこそできたのです」。森社長は、完成の喜びをこう語る。
また、販路開拓という意味でもノウハウは蓄積されている。かつては日本酒は各レストランに1種ずつしか置かれなかったところから、営業努力で複数種が取り扱われるようになったそうだ。
つまり、「イノベーティブなSAKE」の製造から販売まで、アメリカで完結できる土壌が完成しているのだ。小売先も、日系のスーパーにグループの日本食材卸会社から卸すことで、どんどん広がっていっているという。

スパークリング日本酒「澪」の大ヒット
2011年から日本で製造するイノベーティブなSAKEとして、大成功している銘柄がある。スパークリング日本酒「澪」だ。甘酸っぱくジューシーかつ軽い炭酸があり、かなり飲みやすい酒である。そこから派生して、アメリカ向けにややドライな「澪<CRISP>」や、ヨーロッパやアジアに向けて、にごりタイプ「澪<NIGORI>」も誕生している。

「澪は国内外で絶賛されており、ほとんどネガティブな意見を聞かない商品です。アルコール度数が5%と低いので、お酒をあまり飲まない若い方や海外の方にも“入門酒”としても自信を持って薦められます」
澪が発売されてから、森社長は、「宝さんですか? 私澪を飲んでます」「澪を飲んでから日本酒が好きになりました」などと声をかけられることが増えたのだとか。発売から快進撃を続けており、売り上げは直近で3割増のペースで拡大している。

普及のために学校運営やEXPOも
アメリカでは2016年から連結子会社となったミューチャルトレーディングは、日本酒学校も運営している。テイスティングも含めて日本酒の知識を広めるカリキュラムで、年間約400人が受講しているそうだ。

それだけではなく、寿司職人や日本食の料理人を要請する学校も。こちらは2008年に設立したもので、約1カ月のプロ入門編コースと、さらに学びたい人向けの、より高度なメニューを学べるコースがある。
卒業後に日本料理店を立ち上げる人や、自店のメニューに取り入れる人が多いという。

さらに1989年からは、ミューチャルトレーディング主催で毎年「Japanese Food & Restaurant Expo」も開催している。会場は、ニューヨーク、ロサンゼルス、ホノルル。
日本食や日本酒にまつわるものを一挙に紹介する展示会で、出展品は、和牛をはじめとした日本食材は当然ながら、和食器、包丁の研ぎ石、寿司桶、自動寿司握り機など多岐にわたる。日本から140~150社が参加し日本食関連の経営者・シェフ・飲食店関係者2500~2600人が列をなすそうだ。

さらに、2025年には、新規ファン獲得のための取り組みとして、前述したカリフォルニア州バークレーの酒蔵をリニューアル予定だ。バークレーはサンフランシスコのやや東側の街で、涼しい気候とシエラネバダ山脈からの軟水、カリフォルニア米と、酒づくりの要素、テロワールを持っている土地である。
少し北にいくとナパ、ソノマなどワインの産地があり、サンフランシスコからのワイナリー訪問者が多いため、同様に足を運んでもらえる蔵として改装しているのだ。森社長は、「テイスティングルームがあるビジターセンターを新設しています。アメリカのリアルな消費者に酒にふれてもらい、意見を聞く場所にもしたい」と意気込む。
日本食と日本酒を共に売るシナジーとは
3編を通して、宝が日本食と日本酒を世界へ売り込むさまざまな手法を紹介してきた。ここで改めて、そのシナジーを森社長に問うたところ、「同時に提案することで知名度がぐんと高まり、澪をはじめ、数多くの銘柄が3~4年で2桁成長に近い実績を残せている。そして、それらの日本酒に合うメニュー提案から、卸売する日本食材の増加にもつながっている」と相乗効果を語った。
食と酒トータルでの商品開発やサービス、サプライチェーンでの売り場作り、物流網の設計にも貢献しているそうだ。
世界にあるグループ会社と、その取り引き先レストランとのシナジーも発生している。たとえば2024年10月には、「築地太田」および「オータフーズマーケット」という豊洲の鮮魚仲卸業者と輸出を行う企業がグループに入った。
築地太田とオータフーズマーケットでは、アメリカを中心とした世界に新鮮な魚介類を提供している。仕組みはこうだ。日本食レストラン店主がアプリから注文すると、目利きが豊洲市場に競り落としにいく。そして、鮮度を保てる独自パッケージで成田から出荷する。
すると、アジアならその日のうちに、最も遠いニューヨークでも48時間以内に届くそうだ。現在の売れ筋はウニ、海老だという。

「もっと各社のノウハウを共有し、強みを波及できるシナジーをまだまだ発揮していきたいですね。それを各社が次の柱、次の事業に育てていくことで、成長できるようあと押ししていきます」
海外事業は成長が続いており、連結子会社やパートナーは今後も増やしていく予定。それも、ただ闇雲に増やすのではなく、日本食のニーズがあるエリアで、空白地があれば補強し、存在感を増していくという。

伝統的酒造りのユネスコ無形文化遺産登録が追い風に
2024年12月、日本酒業界には朗報があった。日本酒や焼酎、泡盛といった日本の「伝統的酒造り」がユネスコの「無形文化遺産」に登録されたのだ。和食が無形文化遺産になってから11年後の快挙だった。
宝にとってその最も大きな影響は、「世界的に評価される食と酒なのだ。無形文化遺産に登録されるほど貴重なものを、世界中に紹介しているのだ」と、国内外のメンバーが確信を持てるようになったことだという。
これを機に、日本酒のさらなるPRに尽力をしていきたいと森社長。和食が登録された2年後の2015年には、日本の名店の料理人が一大チームを結成し、ミラノ万博で腕をふるった実績もある。この際、宝も帯同し、乾杯の酒はもちろん、各店の料理に合う日本酒を無償提供したそうだ。外務省主催のイベントに澪を提供したこともあったのだとか。

「かつて私たちの事業がそうであったように、日本酒だけをPRしても、海外には広がりません。1951年に海外事業に進出して以降培ってきた流通・販売ルートを今こそ活かして、食と酒をセットで日本食文化として広げていきたい」と微笑んだ。
無形文化遺産を追い風に、まだまだ成長の兆しを見せる宝の日本酒製造・販売事業。大きくシェアを伸ばしてきてはいるものの、世界の酒類市場から見るとごくわずかだ。
アメリカでは全体の0.2%しか占めておらず、まだ大きなポテンシャルがある。
今後は、そのアメリカを最優先に事業を進める予定だ。なぜならアメリカは多国籍民族で、建国から250年と歴史が浅い自由の国。
「日本食だったらこの酒」「日本食レストランでは日本酒を飲む」などと、異文化を丸ごと飲み込んでくれる土壌があるのだ。
日本食材卸事業についてもポテンシャルはある。2023年の日本食レストランは全世界で18万7000軒と、中国料理やメキシコ料理に比べると、桁が2つ少ないそうだ。

ただし、昨今は日本食が全体的に高価になり、カジュアルな外食先として選ばれにくい傾向があるため、もっと大衆よりのメニューを増やすためのアプローチを考えているところだという。
インバウンドに「あんなに安くておいしいものはない」と評価されているおにぎりなど、日本の食文化の裾野が広がる可能性はあると未来を見据える。
「食も酒もハイテク技術ではなく、生活に密着した、生きていくために必然的なものです。そこに少し付加価値をつけたり、喜びをもたらせる企業として貢献していきたいですね。これからもコツコツと、泥臭く広げていきます」
記事をマイページに保存
できます。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら
印刷ページの表示はログインが必要です。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら































無料会員登録はこちら
ログインはこちら