ヘドバンする衝撃の「赤べこ」一体なぜ誕生したか 「ヘッドホンべこ」で常識を覆す野沢民芸の挑戦
「震災後の東北を盛り上げるため、多くの方々が手を差し伸べてくれて、会津の民芸品で新しい取り組みに挑戦していくムードが醸成されていったような感覚ですね。震災前には接する機会がなかった業界の方々との出会いが広がっていきました」

震災前、野沢民芸のべこ商品はカラーバリエーションを数色展開していた程度。しかし、震災後は工房のブランディングにも注力し、工房としてのコンセプトや方向性を整理していくなかで、進化系べこの位置づけも本格的に考えるようになったという。
「コラボのお相手から『こういうことはできますか?』とご依頼を受けたとき、自分でも『できるのかな?』と思いながらも試行錯誤して完成させる、という経験を積み重ねてきた気がします。さまざまなコラボを通じ、それまで自分たちが想像しなかったようなデザインやアイデアを多く目にし、刺激を受けてきました」
コラボ商品も、すべて職人の手作業で生まれる
コラボ商品の割合の多くは限定品やノベルティグッズ。その一方で「諸橋近代美術館」とシュールレアリズムの巨匠、サルバドール・ダリをモチーフにした「ひげべこ」や「タワーレコード」との「犬張子」など、その一部は継続販売中だ。
また、復興プロジェクトの展示作品として制作された青海波べこも商品化の要望を受け、現在まで販売を続けている。
もちろん、それらすべての商品は野沢民芸の職人の手作業によるものだ。
「コラボ商品には当然お相手のブランドカラーなどがありますが、工房として大切にするものづくりのコンセプトとお相手の制作の軸がブレていなければ、できる限りのご希望に添えるようにと思っています。
コラボ商品を作ることで、定番の赤べこの歴史や魅力を、より多くの人に知ってもらえるきっかけになってもらえたらうれしいです」













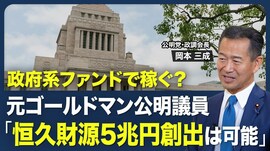
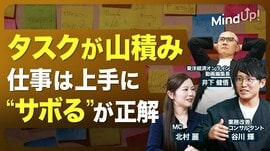

















無料会員登録はこちら
ログインはこちら