ヘドバンする衝撃の「赤べこ」一体なぜ誕生したか 「ヘッドホンべこ」で常識を覆す野沢民芸の挑戦
木の型に和紙を貼り重ねるようにして成形する。糊が乾いたあと、刃物を入れながら枠や型を取り出して、再び貼り合わせる。そうすることで、中身が空洞の立体造形ができあがるのだ。

この張り子という造形技法による民芸品は全国に存在し、会津地方に伝わる張り子玩具・赤べこは、東北地方を代表する民芸品として全国的な知名度を誇る。
忍耐と力強さ、「福」を運ぶ象徴として会津地方で敬われるようになった赤べこの発祥は、今から400年前。同地を襲った大地震で被災した圓藏寺本堂(柳津町)の再建のため、大きな木材を運ぶのために最後まで働き続けた牛が赤い色をしていたという伝説に基づく。
張り子の民芸品としての赤べこは、会津領主となった16世紀の武将・蒲生氏郷(がもううじさと)が、藩の産業として下級武士などに張り子の技法を習得させたことに始まるとされる。
時代を経ても、色褪せない魅力
時代は下り、野沢民芸はそんな会津張り子の工房のひとつとして、当時はこけし工房の職人であった早川氏の父が1962年に西会津町で立ち上げた民芸品工房であった。
赤べこ業界で後発組だった野沢民芸が手がける張り子は、時代を経ても古びないフォルムの美しさと、職人技に裏打ちされたテクスチャーの美しさを最大の特徴とする。
野沢民芸が手がける張り子の特徴が、よく表れているのが「無地べこ」という商品だ。「べこ」の美しい形状と生地感に自負を持つ工房だからこそ可能な商品となっている。














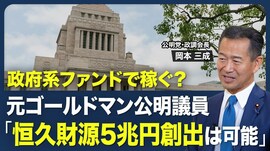
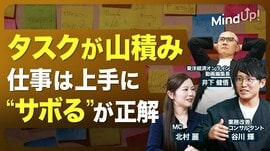

















無料会員登録はこちら
ログインはこちら