それによって「黄金期の特徴だった標準的キャリアのようなわかりやすい比較参照点がなく、互いに嫉妬しあう個人主義が克進して足の引っぱりあいが激化する相対的剥奪感が生まれている」と主張した。
要するに、昭和期のような年功序列による護送船団方式が消え失せてしまった一方で、公正な分配が期待される能力主義を叩き込まれてきた人々は、「でたらめな報酬」が飛び交う状況に戸惑いながら、自分もあやかりたいと願っているのである。
思えば「上級国民」というネットスラングは、一般国民の窮状を顧みず、特定の組織やエリート層が権力を私物化し、特権や利益などに与ることへの怒りがパワーワードとして結晶化したものであったが、その深層には可燃性ガスのような不公平感が充満していたのだ。
2つ目の「アイデンティティのカオス」は、「承認、つまり価値や居場所が与えられているという感覚の領域」の動揺である。常にスキルのアップデートを怠らず、多様なリスクに対応する――そのための自由な付き合い、フレキシブルな働き方と言えば聞こえはいいが、これは愛情やケアといった人間性を養うのに必要な長期的な人間関係を築きにくくする。
職場でも家庭でも個人のライフスタイルに断絶が広がり、ある組織や場所に紐づいているという感覚が薄まってゆき、承認を得ることが困難になっていくのだ。
これらは、いわば平成期に産声を上げた「平成的なカオス」といえる。「昭和的なコスモス」を食い破る形で登場し、実に多くの人々を地獄に引きずり込み、そのカオスは令和になってますます大きくなっている。
ふてほどは平成をほとんど描かなかったが…
この昭和と令和に挟まった平成が「ふてほど」からショートカットされていることはもっと注目されて然るべきであるし、流行語大賞が他を差し置いて影響力の低下が著しいテレビ作品を採用した点についても同様である。
物価高、増税、国民負担率の上昇と暗い話題が続くなかで、「闇バイト」のような日本社会の実相を照らし出す言葉ではなく、マスメディアが創造した「昭和」と「令和」のいいとこ取りのファンタジーを拝借したのである。
「ふてほど」を選ばざるを得ない時代とは、選考委員の“古さ”もあるとはいえ、「失われた30年」とその悲惨な現実を粉飾したくなるほどに深刻な様相を呈している時代といえるだろう。
そして、その根底にはSNSに代表される人々の関心の分断と国民国家の衰退がある。果たしてそのような粉飾は一周回って適切なのかどうか、と問わずにはいられない。
記事をマイページに保存
できます。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら
印刷ページの表示はログインが必要です。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら

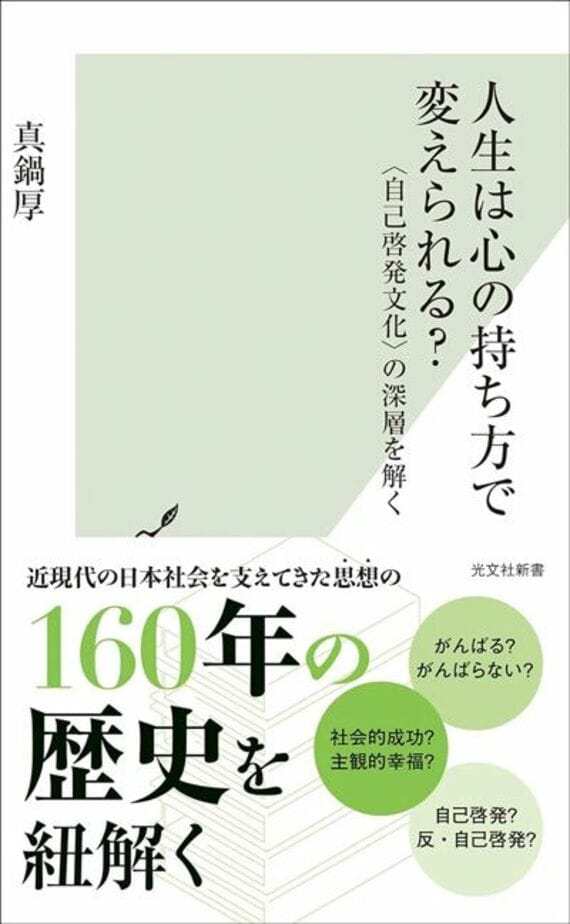





























無料会員登録はこちら
ログインはこちら