魚の獲りすぎをやめないと、日本の魚は枯渇する 2050年に漁獲量ゼロ?墜ちた漁業大国ニッポン

確かに日本の漁獲量減について、外部要因が影響してきたことは否めない。しかし、日本自らが招いた過ちもある。水産庁の魚谷敏紀・資源管理部長は「しっかり資源管理をしていれば、今のような状況にはなっていなかった」と振り返る。
世界は資源管理の時代に突入した
水産物のような生物資源は、獲りすぎると資源量が減り、獲るのを抑えるとまた増え出すとされる。つまり、生物の自然増と釣り合ったペースで漁獲をすることが、漁業を永続させるのには欠かせない。だが日本の場合、魚の“獲りすぎ”を抑えられず、これまでは資源管理ができていなかった。
一方、ノルウェーのような漁業先進国は、政府主導で厳格な資源管理を行っている。1996年に発効した国連海洋法条約を受け、翌97年から日本でも実質的に運用が始まったのが、「TAC」(漁獲可能量)制度だ。魚種ごとにあらかじめTACという“枠”を設けて、実際の漁獲量をそれ以下に抑制しようとする考え方である。最初はサンマやスケトウダラなど、8魚種をTACに設定した。








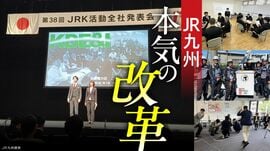




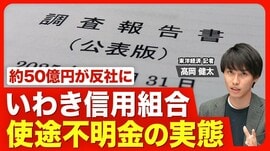

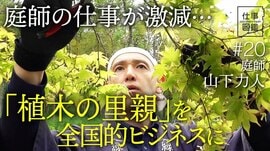
















無料会員登録はこちら
ログインはこちら