実は「世代間ギャップが大きい国」だった日本 「ジャパン・アズ・ナンバーワン」幻影からの脱却
上記のように、新人類世代以降は世代間の距離がほとんどなくなっている。これは見事なほど、先ほど述べた私自身の経験的な実感――団塊世代ないし上の世代とは大きな価値観のズレを感じるが、下の世代との間ではあまり感じない――に合致するものだ。
「“団塊世代的”な世界観からの移行期」としての今
以上のことから、さしあたり次の点が示唆される。すなわちそれは、現在の日本は、“団塊世代的”な価値観からの大きな移行期を経験しつつあるという点である。
これは、最近「昭和」をテーマにした議論やメディアの話題が多いこととも関係しているだろう(「団塊-昭和-高度成長期」はほぼ重なり合う概念である)。つまり“外形的”には見えにくい変化だが、今の日本は人々の価値観や意識において、根本的な変容の時期をくぐり抜けようとしているのだ。
確認的に記すと団塊世代とは、一般的には1947~1949年(特に出生数の多かったいわゆるベビーブームの時期)に生まれた世代を指すが、ここでは(たとえば1950年代半ば生まれまでを含む)もう少し幅広い範囲でとらえている。この場合、医療や介護の分野の議論で以前から「2025年問題」ということが言われており、その趣旨は“1950年生まれの世代、あるいはその前後をなす団塊世代が(「後期高齢者」とされる)75歳前後の年齢を迎え、その結果、大規模な「介護需要」が発生する”という意味である。いずれにしても、こうした年齢になると通常の意味での“社会の一線”からは退いていくことになるので、社会に対する影響力は薄まっていくことになるだろう。
ちなみに、かつて「2007年問題」ということが言われた時期があったが、それは(やはり団塊世代を象徴する)1947年生まれの人々が60歳つまり定年退職の年齢を迎え、その結果として大量の退職者(や技術の承継が途絶えるおそれ)が生じるという趣旨のものだった。
その意味では、“団塊世代的”な価値観や行動様式の影響力が小さくなることはこの頃(2007年)から始まっていたわけだが、しかし一方、企業ないし経済界、そして政治等の世界の“上層部”あるいは日本社会の“中枢部”においては、かなりの高齢層(60代後半~70代ひいては80代)の人々が意思決定の枢要なポジションを担っているのが現実であるため、近年に至るまで――あるいは現在においてなお――“団塊世代的”な価値観は日本社会の基本的なありようを強く方向づけてきたのである。
こうした点については、後編であらためてさらに考えてみよう。
記事をマイページに保存
できます。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら
印刷ページの表示はログインが必要です。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら




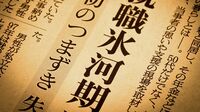


























無料会員登録はこちら
ログインはこちら