多くのまちづくり職人を育ててきたエキスパートの提言。

![週刊東洋経済 2024年5/11号(喰われる自治体)[雑誌]](https://m.media-amazon.com/images/I/51VuN4yK1sL._SL500_.jpg)
私がまちづくりに初めて参画したのは、バブル崩壊の余波が色濃く残る1998年のことだった。
廃れた早稲田商店会の立て直しに奔走した。当時高校1年生だった私がこだわったのが、補助金に依存せず、民間が主導する形のまちづくりだ。取り組みは成功し、全国的にも注目された。
高校3年生のときには全国の仲間とともに会社を設立。以来、さまざまな形で各地の地域活性化をサポートしてきた。
地域活性化に大きなインパクトを与えたのが、2014年から本格スタートした地方創生政策だ。それまで話題に上ることがなかった地方のプロジェクトに、多くの人が関心を持ち始めた。
計画作りをコンサルに丸投げ
それはよい刺激となったが、同時に歪みも生んだ。大型の予算が投じられたことで、地方創生マネーに喰(く)らいつこうと群がる人々が出てきたのだ。地域づくりのノウハウがない自治体は、近寄ってくる地方創生コンサルタントに計画作りを丸投げした。
その結果どうなったか。地方創生に向けて自治体が策定した地方版総合戦略は、どこの自治体も似たり寄ったりの内容になった。
自治体職員はなぜ自前で計画を作れなかったのか。その理由は複数あると思う。

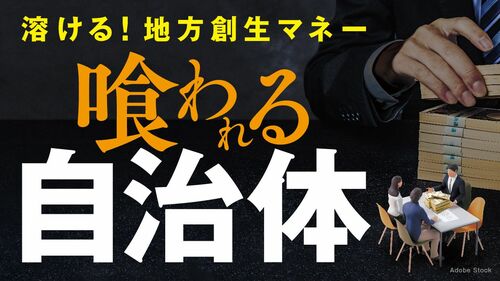

































無料会員登録はこちら
ログインはこちら