痛みや腫れがあり、捻挫が疑われたら、まずどうすればいいのか。
「最も大事なのが、冷やして血管を収縮させて腫れを抑えたり、痛みの感覚を軽減させたりすることです」
「市販の湿布薬を貼るとひんやりした感触があるので、“冷やしている”と思われる方がいるのですが、それは誤解です。湿布は冷やすためではなく、炎症をとって痛みを抑えることを目的に使用するものです。まずは保冷剤などでしっかり冷やすようにしましょう」
と松井医師。保冷剤は長時間あてると凍傷のリスクがあるため、数十分冷やして皮膚の感覚がなくなってきたらいったん休み、熱感や痛みが出てきたら、再び冷やすというサイクルを繰り返す。また、患部を心臓よりも高い位置に保つと腫れがやわらぎやすい。
靭帯が伸びているだけ、あるいは部分的に切れているだけの軽症であれば、こうした応急処置をしつつ、2、3日様子を見る。それだけで症状が治まって日常生活にも支障がなくなり、靭帯も元通りになることが多い。
骨折との違い・判別は?
とはいえ、痛みや腫れの症状は、骨折でも起きる。
一般的に骨折は“歩けないほどの痛み”を伴いやすいが、骨がほとんどずれていない場合などは必ずしもそうではないので、判別してもらうためにも、念のため整形外科を受診したほうがいいだろう。
一方、靭帯が完全に切れていたら、医療機関での治療が必要となる。
捻挫の疑いで整形外科を受診すると、まずは骨が折れていないかどうかをレントゲン(X線)検査で確認する。しかし、レントゲンには骨しか写らないため、靭帯の状態まではわからない。
そこで近年普及しつつあるのが、超音波(エコー)検査だ。靭帯のほか、レントゲンに写らない程度の小さな骨折も確認できる。ただ超音波検査はまだ新しく、どの整形外科でも行っているわけではない。できないときは自覚症状や、ケガをしたときの状況を確認するなどの問診、触診などで診断していく。
捻挫の治療の基本は、ギプスやサポーターなどで患部を固定する保存療法だ。2~3週間程度固定して、症状がある程度治まってきたら、少しずつ動かしていく。
このとき、完治しないうちに捻挫をした場所に負荷をかけてしまうと、靱帯がゆるいままになってしまうため、捻挫を繰り返す要因になりやすいので注意が必要だ。
捻挫を繰り返す人のなかには、歩くときに足をかばうクセがついてしまう人もいる。“将来的に膝痛や腰痛、股関節の痛みなどにもつながる”ので、やはりしっかり治しておくことが大事だといえる。
捻挫予防のための生活の工夫や、予防法などについては、診てもらっている医師や理学療法士に聞いてみるといいだろう。
記事をマイページに保存
できます。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら
印刷ページの表示はログインが必要です。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら



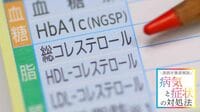












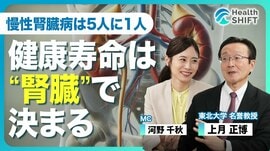





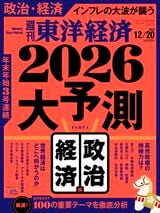









無料会員登録はこちら
ログインはこちら